私は訪問介護事業所で管理者をしています。介護施設・事業所は昨今の物価高で赤字経営の事業所が多いのも事実です。高市政権では医療介護に早急に補助金を出す方針を打ち出していますが、医療介護業界に関わらず、生産性が変わらない市場に資本を投入すればインフレを起こす可能性もあり、さらなる物価高を招き、結局意味がない結果になることも考えられると思います。そういった視点で見ると、基本報酬は変えずに処遇改善加算等の加算の比率を高めて生産性を上げた施設・事業所にインセンティブを与える今の考え方も、あながち間違ってはいないように思えます。この問題や課題について、正確な資料を元に解説してください。
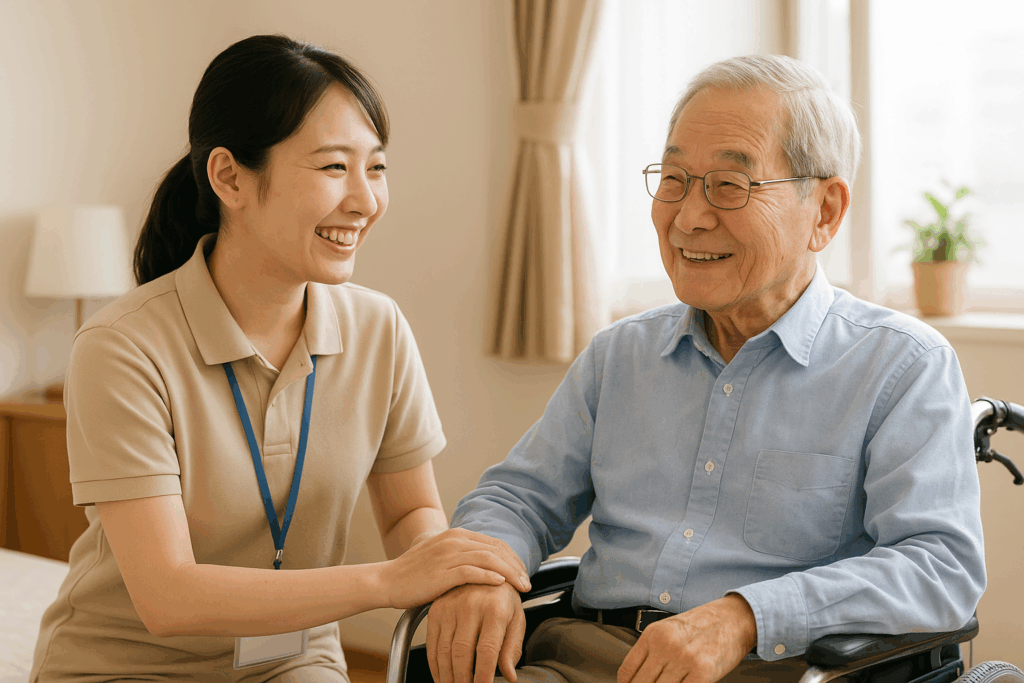
補助金を出しても介護現場は楽にならない?──「生産性を上げる介護」への転換点
介護事業所の赤字問題と補助金の使い方を考える
最近、介護の仕事をしていると「物価高で赤字」「補助金でなんとか持たせている」という声をよく耳にします。
実際、全国の介護施設や事業所では、光熱費や食材費、ガソリン代の高騰により、経営が苦しい状況が続いています。
こうした中、高市政権では「医療・介護機関への補助金支援」を打ち出しました。
現場としてはありがたい話ですが、「それで本当に問題は解決するのか?」という疑問も残ります。
なぜなら、補助金をいくら出しても、現場の生産性(働き方の効率や仕組み)が変わらなければ、また同じ苦しさが繰り返されるからです。
資本を動かしてもモノやサービスの生産量が増えないままお金だけが回れば、インフレが進み、物価はさらに上がります。
結果的に、職員の給料を上げてもすぐに生活コストが追いついてしまう――そんな悪循環です。
「基本報酬」ではなく「加算」で差がつく時代に
現在の介護制度では、サービスごとの基本報酬に加えて、
「処遇改善加算」などの成果や工夫を反映させる加算が重視されています。
これは「頑張っている事業所ほど報われる仕組み」を目指した設計です。
たとえば、職員のキャリアパスを整えたり、ICTを導入して業務を効率化したりすると、
その努力が加算という形で評価され、報酬が上がります。
つまり、「補助金を一律に配る」よりも、「生産性を上げた事業所にインセンティブを与える」方向へと政策が動いているのです。
補助金を“使い方”で未来に変える
とはいえ、補助金や加算を「ただ賃金にあてるだけ」で終わらせてしまうと、現場の仕組み自体は何も変わりません。
これから大事になるのは、次のような「将来の生産性を上げる使い方」です。
- ICT化(記録の電子化・スケジュール自動化など)に使う
- 研修や資格取得支援に充てて職員のスキルを上げる
- 職場環境改善(動線・シフト見直し)に投資する
加算制度の本来の目的は、「介護の質と働きやすさの両立」です。
その方向に資金を回せば、赤字補填だけで終わらない“次の一歩”になります。
介護の未来は「効率化」ではなく「仕組み化」
“効率化”というと冷たく聞こえますが、介護における生産性とは、
「同じ時間でより良いケアを届ける仕組みを作ること」です。
- 記録を音声入力で簡略化
- 移動ルートを見直してムダを減らす
- チームで情報を共有し、連携ミスをなくす
こうした積み重ねこそが、介護の現場を持続可能にする力になります。
まとめ
介護業界を取り巻く環境は厳しく、補助金や加算は確かに“命綱”です。
けれど、それを「未来への投資」として使えるかどうかが、これからの分かれ道になります。
💬 お金を「守るため」に使うか、「変わるため」に使うか。
介護の現場がこの選択をどう進めるかで、5年後・10年後の姿は大きく変わるはずです。




コメント