
はじめに:見送られた改正案と、2027年への問いかけ
令和6年度の介護保険制度改正では見送られたものの、要介護1、2の生活援助を総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)に移行する案は、2027年の次期改正で再び議論の俎上に上がっています。この動きは単なる制度変更に留まらず、日本の社会保障のあり方、そして私たち一人ひとりの「支え合い」の意識に深く関わる問題です。
要介護1,2生活援助の総合事業移行検討の背景(財政逼迫と軽度者支援の効率化)
日本の介護保険制度は、団塊の世代が75歳以上となる2025年を目前に控え、高齢者人口の増加という喫緊の課題に直面しています。この人口構造の変化は、介護保険給付費の増大を招き、制度の持続可能性に対する懸念が強まっています。このような背景から、財政制度等審議会は、介護保険制度の持続可能性を確保するため、「効率的な給付」「給付範囲の見直し」「負担の公平化」という三つの柱を提言しています。この提言の一環として、要介護1、2の軽度者に対する生活援助サービスを地域支援事業、すなわち総合事業へ移行することが強く推奨されています。
この移行の主要な目的は、介護保険給付の効率化を図り、より重度の要介護者に対して専門的なサービスを集中させることにあります。生活援助サービスは、具体的には調理、掃除、洗濯、買い物、薬の受け取りといった家事支援が中心とされています。これらのサービスを、地域の実情に応じた多様な主体が提供することで、より効果的かつ効率的な支援体制を構築しようとする考え方が示されています。
しかし、この動きの背後には、財政逼迫という強力な推進力があることが明らかです。これは単なる効率化に留まらず、実質的な給付抑制、ひいては公的保険給付の範囲を縮小する動きとして捉えることができます。この方向性が進めば、軽度者のサービス利用が制限され、結果的に個人の自助努力や、地域内の互助への依存度が高まる可能性を内包しています。また、「軽度者」と一括りにされる要介護1、2の利用者の中には、認知症を抱える方も相当数存在すると指摘されています。認知症の進行を食い止めるためには専門家による適切な対応が不可欠であり、一律に総合事業へ移行させることの難しさや、サービス質の低下、家族の介護負担の増加といった潜在的な問題が懸念されます。このような軽度者の多様なニーズへの配慮が不足していると、制度の目的と現実の間に乖離が生じる恐れがあります。
総合事業の意義と理念:地域で「支え合い」を育む新たな基盤
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)は、2017年度から全国的に導入された介護保険制度の新たな柱です。その創設には、単なる財政効率化に留まらない、より深い理念が込められています。
創設の目的と厚生労働省が描く「地域共生社会」のビジョン
総合事業の根底にある理念は、市町村が中心となり、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実させることで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援を目指すものです。この事業では、高齢者自身が単なるサービス利用者としてだけでなく、「支え手」側に回ることも想定されており、地域社会での社会参加や生きがいづくりを促進し、元気なうちからの介護予防を継続させることを重視しています。
最終的な目標として掲げられているのは、「地域共生社会」の実現です。これは、高齢者だけでなく、障害者や子どもなど、多様な人々が地域でつながり、互いに支え合いながら自分らしく暮らし続けられる社会を指します。総合事業の理念は、まさに「自助・互助・共助・公助」という多層的な支え合いの概念を現代社会に再構築しようとする、普遍的な考え方を内包していると言えます。特に、高齢者が「支え手」にもなるという発想は、従来の「弱者」としての高齢者像を刷新し、地域における多様な役割創出を目指す点で画期的な試みです。
しかし、この理念は崇高である一方、その実現には大きな課題が伴います。特に、地域住民が自発的に支え手となることへの期待は大きいものの、現代社会のコミュニティの現状を考慮すると、理想と現実の間に既に大きな隔たりがあることが示唆されます。このギャップは、総合事業が直面する具体的な課題へと繋がっていきます。
現状の課題:担い手不足、地域格差、事業所の経営圧迫、認知症高齢者への対応
総合事業は理想的なビジョンを掲げる一方で、その運用には複数の課題が浮上しています。まず、サービスの「担い手不足」が共通の課題として挙げられます。生活支援サポーターやボランティア、NPOといった多様な担い手の育成と定着が進まず、養成しても実働に繋がらないケースが多く見られます。その結果、サービス提供が可能な限られた指定事業所に利用者が集中し、新たな利用者の受け入れが困難になる状況が生じています。
次に、「地域格差」の問題があります。総合事業は市町村が基準や単価を定めるため、各自治体の財政力や介護に対する考え方の違いが、提供されるサービスの質や量に直接的な地域差を生み出しています。これにより、利用者がこれまで通い慣れていたデイサービスを利用できなくなる、あるいは地域によって利用できるサービスの種類や内容が大きく異なるという問題が顕在化しています。
また、総合事業への移行に伴う「介護報酬の減額」は、訪問介護や通所介護事業所の経営を圧迫しています。報酬単価が大幅に削減された自治体もあり、これによりサービス提供時間の制限や、総合事業への参入意欲の低下、中長期的には事業所自体の減少に繋がる可能性が指摘されています。
さらに、「認知症高齢者への対応」も重要な課題です。要介護1、2の軽度者の中には認知症を抱える方が相当数含まれており、認知症の進行を食い止めるためには専門家による適切な対応が不可欠です。しかし、総合事業の担い手が必ずしも専門性を有しているとは限らず、適切な支援が受けられないことで、認知症の進行やトラブルの増加に繋がる懸念があります。
これらの課題は、総合事業が「地域共生社会」という崇高な理想を掲げながら、その実現手段として「財政効率化」を優先した結果、現場の担い手不足や事業所の経営難、地域格差といった新たな問題を生み出していることを示唆しています。これは、理想と現実の乖離が、単なる実装の問題ではなく、政策設計そのものに内在するジレンマである可能性を示しています。「生活援助」が単なる家事代行と見なされ、その専門性が軽視される傾向がありますが、特に認知症高齢者にとっては、生活援助が認知症の進行抑制や生活維持に不可欠な専門的ケアの一環であるという認識が不足している可能性があります。この認識不足は、サービス質の低下や、利用者の状態悪化という負の連鎖を引き起こしかねません。
また、地域差や事業所の減少は、利用者が住み慣れた地域で望むサービスを受け続ける権利を脅かすことになります。これは、地域包括ケアシステムが目指す「住み慣れた地域での生活継続」という理念と矛盾する事態であり、制度が利用者中心の視点を十分に担保できているかという問いを投げかけています。
「自助・互助・共助・公助」の再考:現代日本社会で失われた「間」
今の介護保険制度の課題や問題を真剣に考えている読者さんの中には、現在の日本社会においては、途中の段階を経ずに、自助からいきなり公助~介護保険制度になってしまっていることが問題の根底にある気がするという感覚をお持ちの方も多々いるかと思います。その感性はおそらく、現代日本社会が抱える根深い課題を的確に捉えています。本来、社会保障は「自助・互助・共助・公助」の多層的な支え合いによって成り立っているはずです。
各「助」の定義と、その変遷
社会保障における「自助・互助・共助・公助」は、個人の努力から公的な支援まで、多層的な支え合いの構造を示す概念です。
- 自助(じじょ): 自分の身は自分で守る力です。健康管理や貯蓄、スキルの習得など、将来の困難に備えるための個人の努力を指します。
- 互助(ごじょ): 家族や地域、友人など、身近な人々との支え合いです。日常のちょっとした困りごとを手助けする活動がこれに当たります。日本社会に古くから根付く相互扶助の精神がその背景にあります。
- 共助(きょうじょ): 公的な制度のもとで支え合う仕組みです。健康保険、年金、介護保険などの社会保険制度が代表例です。かつては地域コミュニティやNPO、企業による非制度的な相互扶助も含まれることがありましたが、2000年代以降、社会保険という「制度化された支え合い」に限定される傾向が見られます。
- 公助(こうじょ): 国や地方公共団体が行う救助・援助・支援であり、自助・互助・共助で対応しきれない問題に対し、セーフティネットとして機能します。
歴史的に見ると、これらの概念の解釈は変遷してきました。1980年代の『厚生白書』では、「個人の自立・自助が基本であり、それを支える家庭、地域社会があって、さらに公的部門が支援する三重構造の社会」が理想とされていました。しかし、2000年代以降、「共助」の定義が社会保険に限定され、地域コミュニティは「互助」に位置づけられるなど、その意味合いは変化しています。
介護保険は、様々な社会の課題を解決するため介護の社会化を目指して創設されたものですが、広く一般社会に浸透した一方で、介護保険制度創設以前は普通にあった「共助」という段階を見えなくさせ、自助と公助しかないといった分断をもたらしてしまったこともいがめません。
この「共助」の定義が、かつての地域社会や企業による非制度的な相互扶助から、社会保険という「制度化された支え合い」へと限定されたことは、ユーザーが感じる「間」の喪失に直接的に繋がっています。これにより、制度に縛られない柔軟な支え合いの空間が社会的に認識されにくくなり、結果的に「自助」の次は「公的な制度」という二極化が進んだと考えられます。
また、「自助・互助・共助・公助」はしばしば「補完性原理」に基づいて、下位の主体で解決できない場合に上位の主体が補完するという階層的な役割分担として解釈されます。しかし、この原理は本来、上位の主体が下位の主体の活動を抑制するのではなく、その能力を最大限に引き出し、全体としてのウェルビーイングを高めるためのものでした。日本におけるこの原理の解釈が「義務」の側面を強調し、「公助」の役割を過度に抑制する傾向があることが、現在の「間」の喪失に拍車をかけている可能性があります。
表1: 「自助・互助・共助・公助」の定義と現代日本の課題
| 区分 | 定義 | 現代日本の課題 |
| 自助 | 自分の身は自分で守る力。健康管理、貯蓄、スキル習得など。 | 健康寿命と平均寿命の乖離、十分な資産形成の難しさ。 |
| 互助 | 家族、地域、友人など、身近な人との支え合い。 | 少子高齢化、核家族化、都市部での孤立、地域コミュニティの希薄化による機能弱体化。 |
| 共助 | 公的な制度のもとで支え合う仕組み(社会保険など)。 | 少子高齢化による財政的圧迫、制度の持続可能性への懸念。定義が社会保険に限定され、非制度的な相互扶助が軽視されがち。 |
| 公助 | 国や地方公共団体が行う救助・援助・支援(最後のセーフティネット)。 | 人口減少と高齢化に伴う財政逼迫により、サービスの縮小懸念。 |
「自助からいきなり公助へ」の現状分析と、互助・共助の機能不全
現代日本社会では、個人の自助努力が困難になった際に、身近な「互助」や制度化された「共助」が十分に機能せず、すぐに「公助」に頼らざるを得ない、あるいは公助すら頼れない状況が生まれています。これは、社会全体の「支え合い」の多層性が失われ、脆弱な構造になっていることを意味します。
「互助」の機能弱体化は、少子高齢化、核家族化、都市部での孤立の増加といった社会構造の変化と密接に関連しています。内閣府の調査でも、自治会の課題として「近所付き合いの希薄化」が8割以上の市区町村で挙げられており、近所付き合いの度合いが時代とともに低下していることが示されています。このような状況では、日常のちょっとした困りごとを気軽に助け合える関係性が築かれにくくなっています。
さらに、少子高齢化による人口減少と財政逼迫は、国や地方自治体による「公助」の弱体化という懸念も高めています。最後のセーフティネットである公助が縮小すれば、社会全体の支えが危うくなることは避けられません。
この状況は、「自立とは依存先を増やすこと」という考え方と深く関連しています。自助が困難になった際に、頼れる「依存先」が家族や地域に少なく、公助に集中してしまう、あるいは公助が弱体化して頼れる先がなくなることが、現代社会の脆弱性の根源にあると考えられます。また、日本社会は国際比較で「見知らぬ他者と助け合う意識が弱い」と指摘されており、これが地域コミュニティにおける「互助」の広がりや、制度化された「共助」以外の社会連帯を阻害する要因となっています。この意識は、単なる政策や制度の変更だけでは解決できない、より深い社会文化的な課題として認識されるべきです。
宗教的背景を持つ社会における互助・共助の役割から学ぶ示唆
宗教的背景を持つ諸外国における社会では、互助や共助がより強く機能する可能性を秘めています。宗教とは本来、年齢・性別・人種・障害の有無などの垣根を越えた関係性をもたらし、地域の福祉に活かす要素を担うべきものです。災害時の協力協定、自殺防止対策、児童福祉施設や生活困窮者・障害者施設の設立・運営、日本語勉強会や営繕活動など、多岐にわたる社会貢献活動を積極的に行う基盤となるべきです。本来これらの活動は、制度や契約を超えた「互助」の重要性を強調し、より普遍的な「寄り添い」を体現する場として機能されうるものです。実際の現実社会においてはマイナス面が目立ちがちではありますが。本来、日本社会に不足しているとされる、血縁や地縁に限定されない、より普遍的な「共助」の精神を育む「見知らぬ他者と助け合う意識」を育む上でモデルとなり得るものになるべきだと考えられます。
総合事業の「あるべき姿」と役割:多層的な支え合いの再構築へ
総合事業が、単なる介護保険給付の効率化に終わらず、真に「地域共生社会」を築くための基盤となるためには、現在の課題を乗り越え、その役割とあるべき姿を再定義する必要があります。
地域資源の活用と多様な担い手の育成・確保
総合事業の成功には、ボランティア、NPO、民間企業、協同組合など、地域の多様な主体が生活支援・介護予防サービスを提供することが不可欠です。担い手育成の成功事例からは、住民の中から「生活・介護支援サポーター」を養成し、有償ボランティア活動を導入することが有効であることが示されています。例えば、千葉県流山市のNPO法人市民助け合いネットは、高齢者が低額な謝金で日常生活を支え合う有償ボランティア活動に取り組んでいます。また、地域の「集いの場」を整備し、住民が主体となった介護予防活動を定期開催することも有効です。介護助手のような新たな担い手の普及促進も進められています。
「生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)」の配置や協議体の設置は、地域の支え合い体制づくりを推進し、ニーズとサービスのマッチング、資源開発、関係者間の意識共有に貢献します。
「多様な担い手」の確保は喫緊の課題ですが、その際に重要なのは、単に数を増やすだけでなく、必要なスキルや専門性をどう確保するかという点です。特に認知症高齢者への対応を考えると、専門職の関与や、担い手への継続的な研修が不可欠であると考えられます。無償のボランティアだけでは限界がある中で、「有償ボランティア」という形態は、経済的インセンティブと社会貢献意欲を両立させ、担い手の裾野を広げる現実的な解決策となり得ます。これは、市場の力を活用した新たな「互助」の形とも言えるでしょう。地域差を解消するためには、国が示すガイドラインに加え、成功事例の横展開や、自治体間の連携強化(都道府県による後方支援体制の充実など)が求められます。
表2: 総合事業における主要課題と解決策の方向性
| 主要課題 | 解決策の方向性 | |||
| 担い手不足 | 多様な担い手(NPO、民間企業、ボランティア、協同組合)の育成・確保。 | 生活支援コーディネーターの配置と活動支援。 | ボランティアポイントの活用や有償ボランティア制度の導入。 | 介護助手などの新たな担い手の普及促進。 |
| 地域格差 | 国・都道府県による財政的・技術的支援の強化。 | 成功事例の共有と横展開の促進。 | 市町村間連携の強化。 | |
| 事業所の経営圧迫 | 総合事業の報酬単価や運営基準の見直し、適切な評価制度の導入。 | ICT活用による業務効率化。 | ||
| 認知症高齢者への対応 | 専門職(リハビリテーション専門職等)の関与の強化。 | 担い手に対する認知症ケアに関する継続的な研修の実施。 | 認知症の進行抑制に資する専門的支援の確保。 |
市場の役割と「冗長性」の確保:新たな互助・共助の担い手としての可能性
従来の社会保障論では見過ごされがちだった「市場」が、「互助」や「共助」の新たな担い手になりうるとの指摘があります。これは、企業やNPOが提供する有償サービスが、家族や地域コミュニティの限界を補完し、多様なニーズに応える可能性を秘めていることを意味します。
システム設計において「冗長性」(重複や複数の手段)を確保することは、特定のシステムが機能不全に陥った際のリスクを低減し、システム全体のレジリエンスを高めます。これは、厳格な役割分担ではなく、複数の主体が相互に補完し合う多層的な支え合いの構築を意味します。市場を「互助・共助」の担い手として位置づけることは、福祉サービスを単なる「お世話」から「多様な選択肢」へと転換させ、利用者の自立支援にも繋がります。例えば、高齢者自身がサービス提供者となる「プロシューマー」的な役割を市場の中で見出すことも可能です。
冗長性の確保は、既存の公的制度や地域コミュニティの「隙間」に落ち込む人々を救済する上で極めて重要です。市場がその隙間を埋める役割を担うことで、誰もが取り残されない社会の実現に貢献できます。これは、特に「見知らぬ他者と助け合う意識が弱い」という日本の社会特性を補う上で有効な視点です。市場を新たな担い手として育成するためには、公的部門(国や自治体)が、法制度の整備、予算、ネットワーキング、情報共有といった形で、市場の創出と育成を支援する役割を果たす必要があります。
利用者中心の視点と、自立支援・重度化防止の推進
総合事業は「高齢者本人の参加意欲を基本に、地域生活の中で活動性を継続的に高める取組」を進める方向への転換を目指しています。これは、できないことを「お手伝い」するだけでなく、「できていることの継続」と「改善可能なことを増やす」支援により、高齢者の自立度を向上させる視点です。例えば、長野県川上村では、住民サポーターが「生活・介護支援サポーター」として活動し、専門職が不足する中で地域に不可欠な担い手となっています。
要介護1、2の軽度者であっても、生活援助がなければ状態が悪化する可能性があると指摘されており、適切な生活支援は重度化防止に不可欠です。特に認知症高齢者にとっては、専門的な見守りや対応が進行抑制の分かれ道となります。
「自立とは依存先を増やすこと」という視点を実践するためには、利用者中心の自立支援とは、単に「自分でできることを増やす」だけでなく、多様な「依存先」を確保し、それらを活用することで、より豊かで安定した生活を送れるように支援することです。総合事業は、その「依存先」の多様化を地域で実現する役割を担うべきです。介護予防は、単なる運動教室だけでなく、社会参加、生きがいづくり、地域コミュニティとのつながりなど、多角的なアプローチが必要です。総合事業は、これらを統合的に提供するプラットフォームとなることで、真の重度化防止に貢献できます。
表3: 地域包括ケアシステムにおける総合事業の成功事例(抜粋)
| 自治体名 | 主な取り組み内容 | 地域共生社会への貢献 |
| 熊本県上天草市 | 住民による検討委員会、ニーズ調査、介護予防拠点整備(旅館改修)、ホームヘルパー養成、緊急通報システム無償設置、住民主体介護予防活動。 | 地域住民が主体となり、多様なニーズに応える生活支援と見守り体制を構築。離島という特性に応じた地域包括ケアを実現。 |
| 新潟県長岡市 | 市内に13カ所のサポートセンター設置、医療・介護・住まい・予防・生活支援のワンストップ提供、地域住民との交流イベント。 | 小地域完結型の支援体制を構築し、住民が身近な場所で切れ目なく支援を受けられる安心感を醸成。 |
| 東京都世田谷区 | 5つの要素(医療・介護・予防・住まい・生活支援)をバランス良く取り入れた体制、約70団体が連携する「せたがや生涯現役ネットワーク」。 | 都市部の高齢化に対応し、地域資源を活かした持続可能なケアの仕組みを構築。高齢者の社会参加と役割創出を促進。 |
| 鳥取県南部町 | 空き家を活用した低所得者向け住まい整備、配食・見守りを地域ボランティアが担う、地域交流スペース付き共同生活。 | 中山間地域における住民主体の介護予防と生活支援を実現。年金暮らしの高齢者が安心して暮らせる環境を整備。 |
| 長野県川上村 | 住民の中から「生活・介護支援サポーター」を養成し、有償ボランティア活動を導入。行政とサポーターが協働でサービスを創出。 | 専門職不足を補う地域に不可欠な担い手を育成し、住民と行政の距離を縮める関係性を構築。 |
| 千葉県流山市(NPO法人市民助け合いネット) | 高齢者が低額な謝金で日常生活を支え合う有償ボランティア活動。 | 市場の力を活用した新たな「互助」の形を提示。経済的インセンティブと社会貢献意欲を両立させ、担い手の裾野を拡大。 |
| 北杜市 | 住民ニーズ調査に基づき、地域づくりによる介護予防を推進。住民ボランティアが活躍する通いの場を創出。 | 高齢者の自立度向上と認定率低下に貢献。住民同士の絆を深め、地域力を向上。 |
| 静岡市 | 独自の報酬基準によるミニデイサービスや体操の会を推進。住民の自主活動としての定着を支援。 | 住民の自立支援と生きがい創出に繋がり、活動の継続性を確保。行政と住民の協働関係を構築。 |
未来への提言:私たち一人ひとりが「支え合い」の担い手に
2027年の介護保険制度改正は、日本の社会保障システムが直面する大きな転換点です。総合事業の役割とあるべき姿を追求することは、私たち一人ひとりが「支え合い」の担い手となるための道筋を探ることに他なりません。
政策提言:制度設計における柔軟性と地域の実情への配慮
まず、制度設計においては、より一層の柔軟性と地域の実情への配慮が求められます。担い手確保と事業所の持続可能性のためには、総合事業の報酬単価や運営基準について、地域の実情に応じた柔軟な設定を可能にする、あるいは適切な評価を行う必要があります。現在の報酬減額は、サービス提供体制の維持を困難にし、結果的にサービスの質の低下や提供事業所の減少を招く恐れがあります。
また、要介護1、2の軽度者であっても、その実際の生活状況や認知症の有無を考慮し、必要な介護保険サービスが確実に提供されるよう、給付範囲やサービスの質を保証する仕組みが不可欠です。画一的な線引きではなく、個々のニーズに応じたきめ細やかな対応が、真の重度化防止と利用者の生活の質の維持に繋がります。さらに、市町村間のサービス格差を是正するためには、国や都道府県による財政的・技術的支援の強化、そして成功事例の共有と横展開を積極的に行うべきです。これにより、全国どこに住んでいても一定水準のサービスが享受できる環境を整備することが重要です。
地域住民・事業者・行政の連携強化の重要性
「地域共生社会」の実現には、多職種・多機関連携が不可欠です。医療・介護専門職だけでなく、地域住民、NPO、民間企業、ボランティア、そして宗教団体など、多様な主体が連携し、情報共有と協働を深めることが求められます。行政は、単なるサービス提供者ではなく、地域全体のコーディネーターとして、多様な担い手とニーズを繋ぎ、新たな支え合いの仕組みを創出する役割を強化すべきです。
また、高齢者自身が「支え手」となる活動をさらに推進し、地域活動への参加を促すための仕組み(例:ボランティアポイント、介護助手制度)を充実させるべきです。多くの高齢者が「社会とのかかわりを持って生活したい」という意欲を持っていることが調査で示されており、この意欲を具体的な活動に繋げる支援が重要です。住民の主体的な参画が、地域コミュニティの活性化と持続可能な支え合いの基盤を築きます。
「支え合い」の文化を育むための具体的な一歩
希薄化した「互助」を再構築するためには、従来の地縁・血縁に頼るだけでなく、共通の関心や目的を持つ人々が集まる「ゆるやかなつながり」を育む場(サロン、趣味の会など)を増やすことが有効です 6。このような場は、新たな人間関係を構築し、互いに助け合う機会を自然に生み出します。
特に、宗教団体が持つ「信頼関係の醸成」「垣根を越えた包摂」「人間的な寄り添い」といった知見は、現代社会の「互助」機能の強化に大いに貢献しうるため、行政や地域社会が積極的に連携を模索すべきです。宗教コミュニティが持つ、制度や金銭的利益を超えた「助縁」の精神は、現代社会に不足している人間的なつながりを再構築する上で示唆に富んでいます。
そして最も根源的な一歩は、「自立とは依存先を増やすこと」という視点を社会全体で共有し、他者に頼ること、頼られることを肯定的に捉える文化を育むことです 15。これは、個人が孤立せず、多様な支援の選択肢を持つことで、より豊かで安心できる生活を送れるようにするための基盤となります。総合事業の議論を通じて、私たち一人ひとりが「支え合い」の担い手として、この多層的な社会の再構築に貢献していくことが、持続可能な未来を築く鍵となるでしょう。


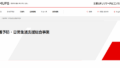
コメント