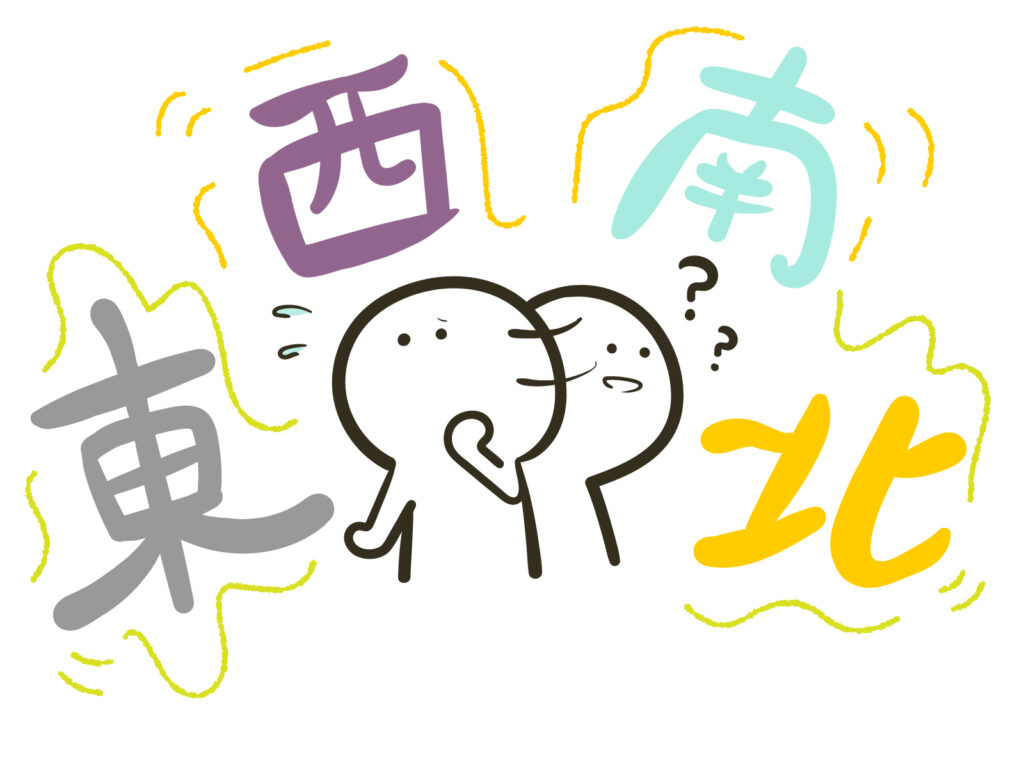
訪問介護事業所のサービス提供責任者をしていると、さまざまな利用者さまと出会いますが、さまざまは私たちサービス提供者も同じです。
人材不足の中、新しく入職していただいたヘルパーさんは、超貴重な存在はありますが、時に?といった人もいなくはありません。
今回は、「超方向音痴のヘルパーさんが入職したら」、といった場面の対処法について考えてみたいと思います。
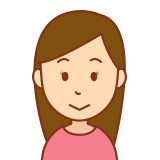
新しく入職した職員に複数回の同行をして独り立ちさせたのですが、極度の方向音痴で、独り立ち後も利用者宅までひとりで行けず、事務所に行き方を聞いてくることが多いスタッフがいます。サービス提供責任者も、分かりやすい道順で説明したり、スタッフ本人に対しても行き方が分かったのか何度もたずね、その時は分かりましたというのですが、実際に一人で入ってもらうと、訪問時間を過ぎているので利用者宅までたどり着けず、事務所に行き方の相談お電話が入ることがしばしばあります。このようなスタッフに対して、どのように行き方を覚えてもらえばよいでしょうか? ケアプランに沿ったサービス提供ができず困っています。サービス提供責任者として、当該スタッフに対してどのようにアドバイスや教育をしたらよいかを教えてください。
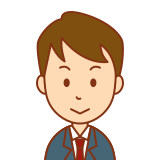
お困りの状況、お察しいたします。サービス提供責任者として、利用者さんへの安定したサービス提供は最重要課題であり、スタッフの「道順問題」がそれに影響しているとなれば、具体的な対策が必要ですね。ヘルパーさんの特性(極度の方向音痴)を踏まえつつ、ケアプランに沿ったサービス提供を可能にするための教育・アドバイス方法について、いくつかご提案させていただきます。
1. 「道順を覚える」ための具体的なサポート・教育方法
単に「分かりやすい道順」を口頭や簡単なメモで伝えるのではなく、極度の方向音痴の方、あるいは空間認知に特性があるかもしれない方を想定し、「視覚化」「手順化」に特化した対策を試みましょう。
(1) 道順の「完全なマニュアル化」と視覚情報重視
- 写真付きマニュアルの作成:
- 利用者宅までの道順のポイントとなる場所(大きな建物、曲がり角、信号、目印となる店など)ごとに写真を撮り、「この写真の場所に来たら右に曲がる」といった具体的な指示を添えたマニュアルを作成します。
- スタッフ自身に、一度同行した際に写真を撮らせて、自分にとって分かりやすいマニュアルを作らせるのも有効です。
- 「帰り道の景観」も記憶に残りやすいので、利用者宅を出てから事務所(または次の利用者宅)までの写真も作成に含めましょう(帰り道の景色と行き道の景色が違って見えることがあります)。
- 地図アプリの活用指導(GPS機能の利用):
- スマートフォンの地図アプリ(Googleマップなど)の操作方法を具体的に指導し、訪問先を事前に登録させます。
- 「現在地」が示されるGPS機能の活用は、方向音痴の方にとって非常に有効です。音声ナビゲーションを利用することも検討させます。ただし、訪問中の私用スマホ利用は原則禁止している事業所もあるため、業務利用としてのルールを明確に定める必要があります。
- 手書き・簡略化された地図の作成:
- 詳細な地図ではなく、主要な目印と曲がり角だけをデフォルメした「ルートマップ」を一緒に作成します。これにより、情報過多による混乱を防ぎます。
- 目印は「コンビニ」「大きい信号」「赤い屋根の家」など、具体的に指示します。
(2) 複数回・多様な同行訓練の実施
- 「道順確認のみ」の同行(予行演習):
- サービス提供の同行とは別に、利用者宅への「行き方・帰り方」の確認だけを目的とした同行を複数回実施します。
- サ責が先に歩くのではなく、スタッフ本人が「ナビゲーター」となり、サ責が後ろから付いていく形式で歩かせ、途中で立ち止まって「次はどちらに進みますか?」「目印は何ですか?」と質問し、その場で記憶の定着を促します。
- 時間帯を変えての同行:
- 昼間と夜間、あるいは天候が異なる日など、景色の見え方が変わる状況での同行を試みます。
- 「分かったつもり」を防ぐ確認方法:
- 口頭で「分かりましたか?」と聞いても「はい」と答えてしまうため、「この信号を渡ったら、何が見えますか?」「右に曲がったら、何軒目の家ですか?」など、具体的な視覚情報を問う質問に切り替えましょう。
2. 特性の可能性を踏まえたアドバイスと環境調整
もし、ご指摘のように発達障害的な特性(特に空間認知や順序立てた作業の苦手さ、あるいは短期記憶の弱さ)が背景にある場合、感情論で叱責したり、精神論で「頑張れ」と言っても改善は難しく、適切な環境調整と具体的な教育方法が鍵となります。
(1) 業務に支障が出ていることの明確な伝達
- 状況の共有:
- 「訪問時間が遅れると、利用者様に迷惑がかかり、ケアプラン通りのサービス提供ができなくなる。これは重大な問題である」という事実を、感情的にならずに、冷静に伝えます。
- 「あなたは方向音痴だ」と指摘するのではなく、「利用者宅への到着に時間がかかるという問題が発生している」と事実と結果にフォーカスして伝えます。
- ルールの設定と徹底:
- 「道に迷った際は、まずどこまで戻ってから電話をするか」「訪問予定時刻の何分前には必ず訪問先に到着するようにする(予備時間の設定)」など、具体的な行動ルールを一緒に決めます。
(2) 担当エリア・訪問ルートの調整
- 担当エリアの限定:
- 当面の間、訪問エリアを限定し、慣れた数件の利用者宅のみを担当してもらいます。エリア内の地理に慣れてきたら、徐々に拡大することを検討します。
- 訪問ルートの固定化:
- 可能な限り、ルーティン化しやすい訪問スケジュールを組み、毎日同じルート、同じ利用者宅を訪問する頻度を増やします。新しい訪問先への導入は、他のスタッフよりも時間をかけて行う必要があります。
3. 事業所としての対応(相談先の検討)
スタッフの困りごとが、一般的な努力では解決しがたいレベルにある場合、事業所として外部の支援を検討することも視野に入れます。
- 産業医や保健師への相談(いる場合):
- スタッフの健康面や精神面を含めた相談窓口として活用できます。
- ハローワークや障害者就業・生活支援センターへの相談:
- スタッフに発達障害などの可能性がある場合、職業生活における困りごとや指導方法について専門的なアドバイスを受けられる場合があります。スタッフ本人の同意があれば、これらの機関と連携して支援計画を立てることも可能です。
この問題は、スタッフ個人の問題であると同時に、サ責として、そのスタッフが最大限能力を発揮できるよう配慮し、「教え方・伝え方」を変えることで解決を目指す、事業所の課題でもあります。根気強く、上記のような視覚化・手順化を徹底した教育を試みてください。
当たり前のことですが、利用者さまもいろいろな方がいるのと同じで、私たち支援を提供する側にも様様な人がいます。せっかく介護・障害福祉サービスの分野で働いてみたいと思ってくれた人たちに対して、いかに気持ちよく、かつ戦力になるように働いてもらうかは、事業所の問題にとどまらず、我が国の現状にとって非常に大切なことです。
本ブログの読者の皆さまも、お悩み事やうまく言った事例等がありましたら共有してゆきましょう‼


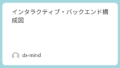

コメント