
訪問介護事業所の倒産・閉鎖、休廃業の流れが止まりません。人材不足も深刻で「保険あってサービスなし」といったワードも散見されます。訪問介護や訪問系の障害福祉サービス事業所の将来はどうなってしまうのでしょうか? 不安は尽きません。
サービス提供責任者でありながら直接支援も多い私が、時間の都合がついたため、久しぶりに事業所間交流の集まりに参加する機会を得ることができました。他事業所の最近の事業運営の状況を聞くことができ、今の状況を知る良い機会になりました。
訪問系事業所の現状についてですが、大きく分けると二つのグループがあるように感じました。
ひとつは、ヘルパーもサービス提供責任者も年齢が上がり、新規採用も思うようにできず、事業規模縮小フェーズに入っている感のある事業所です。皆がんばっているので、努力が実を結ばないケースなのですが、一方で、外国人ヘルパーの積極的な登用をはじめ、かなりのお金をかけてでも積極的に若い人材の採用に力を注いでいる事業所などがあることが分かりました。
特に後者の事業所は、使える制度は積極的に活用してゆく、といったアクティブな姿勢が感じられました。例えば近年、大学に通う過半数が奨学金を得ながら通学しているのですが、東京都の独自施策で介護分野に従事すると奨学金の全額返済制度があります。こういった制度も積極的なピールして若い人材に対して積極的にアプローチしている事業所もあります。
もちろん、売り上げベースで余裕のある事業所が可能な方法なのですが、できることはやる、やれることはやる、といった気負いがある事業所も、地域の身近な所にもあることに触れて感化されました。
人間は年齢ではないのですが、やはり、若い人が多いところが時代の変化についてゆけている感があります。もちろん、それも戦略的におこなわなければ達成することができない課題ではあります。
新しいことに消極的な人もいれば積極的な人もいます。それに拒否感を抱く人もいれば変化を楽しめる人もいます。それは、介護業界においても同じです。介護事業所を経営・運営する人は、どれだけ新しい風を自事業所に取り込めるかが今後の事業所運営の肝になります。その想いは、自事業所の存続にはおさまらず、介護業界全体、障害福祉サービス事業所全体の未来を切り開くものになるのだと思います。それは、自分たちの事業所の存続といった話なのではなく、福祉や介護の歴史を紡ぐ大きな流れに関わるものだと思うのです。
経営者の皆さま、管理者の皆さま、サービス提供責任者の皆さま、目の前の仕事にただただ追われるのではなく、他事業所や地域との交流の中で、どうか、自分たちが歴史のバトンをつないでゆく大切な仕事に関わっているのだという自覚を持ちながら毎日を過ごしていただきたいと思います。私もがんばります。
「全部盛り」は難しいのは自覚していますが、お給料もそこそこ稼げて、しかも対人援助の仕事の楽しさも味わえて、さらに最新のICTにもついてゆけて、その経験と実績が他の仕事でも生かせるようなレベルに達せられる、それでも介護や福祉の仕事に携わってゆきたい。。。わかっていますが、こんな仲間を一人でも創ってゆけたらと思うのです。。。
この仕事が好きだから、心からそう思えるから、課題山積の現状の中でも、何とかがんばろうと思っています。。。


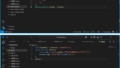
コメント