
介護保険の時期改正は、2027年です。3年ごとに見直される介護保険。直近の改正が令和6年度で、今年度は経過期限を過ぎて本格運用の年になります。もちろん、3年ごとの改正では、急速に変化する社会情勢に対応できないため、都度都度、運用の見直しや補助金といった「つなぎ」の制度が矢継ぎ早に打ち出されています。皆さまは、これらの制度の変更や追加についてゆけていますでしょうか?
さて、課題山積な介護保険制度をめぐって、様々な議論が活発に行われています。その主たるものとして、厚生労働省所管の『「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会』や、財務省所管の『財政制度等審議会 財政制度分科会』が開催されています。財務省は、ネット民にかなり叩かれていますね。国債に頼る日本のひっ迫した財政は、IMF(国際通貨基金)からも警告を受けている国際問題です。
少しでも社会問題に関心のある人は、この先この国は一体どうなってしまうのだろうか?、と感じている人も少なくないと思います。人口爆縮、超少子超高齢化社会、社会保障制度の行き詰まり、国際プレゼンスの低下、工業力の低下、新産業への転換不全、自国通貨の相対的価値低下、夫婦別姓同姓選択制すら通らないガラパゴス化した法制度、移民問題、破滅的災害への危惧、待ったなしのインフラの老朽化などなど、問題や課題を上げたらきりがないくらい出てくる社会になってしまいました。
で、今回のテーマは、2027年の介護保険の法改正を大胆予測、です。予測といってもできることは限られていますし、課題は出尽くしている感があります。議論されつつも、令和6年度改正で見送られた内容も多々あります。落としどころは、どんな感じになるのか、ということを反論もあると思いますが考えてみたいと思います。
1. 現状の問題点と課題
まず、日本が抱えている現状と課題ですが、やはり、超高齢化による要介護者の急激な増加と、介護を担う人材の深刻な不足、現役世代が高齢者を支えるというこれまでの世代間扶養が限界に達していること、現役世代の社会保険料負担が限界に達していること、貯蓄や金融資産保有が世代の内外でバラツキがあることなど、上げたらきりがありません。また、高齢者の人口や比率も、既にピークアウトしている地域も多々あることなど、地域間でも現状や課題が一律ではないことが分かっています。
2. 俎上に上がっている事項
これまでも、そして、現在でも議論されている俎上に上がっている方向性として、デジタル化や大規模化・協働化などによる間接業務の効率化による生産性の向上、同一建物内の利用者を対象とした訪問介護サービスのさらなる適正化、人材紹介会社への規制強化と適正化、軽度者に対する生活援助の総合事業への移行、金融資産や金融所得を加味した利用者負担の見直し、ケアプランの利用者負担の導入などがあります。
さらに、全国一律に捉えるのではなく、中山間・人口減少地域、大都市部、一般市等に分けて、それぞれの地域が抱える現状や課題に応じてメリハリのある制度にしてゆくことが検討されています。
3. デジタル政府化との連動
日本は現在、ガバメントクラウドの整備など、デジタル政府化を進めています。この流れと連動するように、介護・福祉・医療分野においても、マイナ保険証の運用は既に始まっていますが、介護情報基盤の整備と運用も、次期改正においては介護報酬との連動やインセンティブが盛り込まれることが大いに想像されます。
デジタル化、ICT化においてもハード面の支援ばかりではなく、デジタル中核人材の配置や育成が盛り込まれるなど、人への投資も今後はおこなってゆかなければならない分野だと思います。
4. 2027年度改正未来予測
介護報酬はもはや上がる余地はあまりないかもしれません。もしかしたら、中山間・人口減少地域に対する加算の原資に、大都市部の介護報酬が当てられるかもしれません。
また、東京などの大都市部では、デジタル化による生産性向上はもはや必須となることが大いに予想されます。介護情報基盤の活用やケアプランデータ連携システム等の導入などは、未対応の場合は実質的な減算になるかもしれません。
さらに、大規模化や協働化に対するインセンティブは現在では処遇改善加算の選択項目でしかありませんが、これらに対するインセンティブはさらに高められることも予想されます。
個人的な見解ではありますが、1法人1事業所といった小規模な訪問介護事業所がそれぞれバックオフィスを個々に実施している現状は、大いに無駄があると感じています。研修の共同開催やシステムの共有など、できることはたくさんある気がします。
介護保険は2000年に創設された制度ではありますが、もともと介護や福祉は長い歴史があり、その担い手の多くがビジネスとは違った分野の人たちによって成り立ってきたため、ビジネス感覚に疎く、また、法令の読み込みがあまい経営者や管理者等が多いことも大いに問題だと思っています。
平成時代の介護保険や障害福祉サービスと現在の令和のそれは別物と考えた方が良いくらい変貌しています。仮に介護報酬を少し上げたくらいでは、少しではなく大きく上げたとしても介護福祉業界に多くの人が集まるようにはならないでしょう。現在俎上に挙げられているものの多くは、次期改正に取り入れられてゆくことが大いに想像されます。今のうちから将来を見通して対策を講じてゆくことが、生き残りをかけた最低限やらなければならないことだと、個人的には思います。
介護職員はその経験を活かし、たとえ介護業界を離れたとしても身に着けた対人スキルによって、他業界でも活躍できるような人材として育て、サービス提供責任者等は、そのコーディネート能力やバックオフィスの事務作業のスキルを高めることで、どの業界に行っても渉外スキルを活かして活躍したり、デジタル人材として様々な分野でも活躍できるような人材となってゆくことが望ましいと、私は考えています。

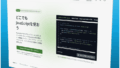
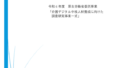
コメント