
導入:病院から「自宅」へ向かう、不可逆的な大潮流
1.1. 在宅医療・訪問看護の需要はどれだけ伸びているのか
日本の医療制度は今、「病院完結型」から「地域・在宅完結型」へと、不可逆的な大転換期を迎えています。これは、超高齢社会の進展と、前回の記事で解説した公立病院の経営難に象徴される医療費の抑制圧力、そして国民皆保険の持続性というマクロな課題が背景にあります。
在宅医療のニーズは、私たちが体感する以上に急速に高まっています。2020年から2040年にかけて、75歳以上の訪問診療の需要は43%増、特に85歳以上では62%増と、劇的な増加が見込まれています。
この大転換を支える核となるのが、訪問看護事業所です。地域包括ケアシステムの構築という国の政策目標に基づき、急性期病院での長期入院を減らし、医療と介護の連携を強化して住み慣れた地域での生活継続を可能にするため、訪問看護ステーションの役割は増大の一途をたどっています。
1.2. 現場の光と影:サービス増加と「不正」の懸念
在宅医療の推進は、患者が自宅で質の高い医療を受けられるという大きな「光」をもたらす一方で、サービスの急拡大は、その裏側でいくつかの深刻な「影」も生み出しています。ご指摘の通り、訪問看護事業所の増加とともに、不正請求の報道も散見されるようになりました。
本稿では、病院から在宅への移行の具体的な課題、そして健全な在宅医療の継続を妨げかねない構造的な問題点と、その対策について深掘りします。
第1部:病院から在宅へ— 「スムーズな移行」を阻む壁
在宅医療を成功させる鍵は、病院に入院した患者が自宅へ安心して戻れるよう、切れ目のない情報とサービスを提供することです。しかし、そのプロセスにはいくつもの障壁が存在します。
2.1. 病院側の「退院支援」体制の遅れ
高齢患者の入院では、退院後に介護サービスが必要となるケースが多いですが、「退院間際になって要介護認定を受けていない」ことが判明すると、退院が遅れてしまうという問題が頻繁に発生します。これは、病院にとっての病床回転率の低下につながり、患者にとっても望まない長期入院の原因となります。
この問題を解決するため、病院側には「入院時支援加算」などの制度を活用し、入院サポートセンターなどを設置して入院前から早期退院を意識した支援を行うことが求められています。
2.2. 情報連携の不十分さと患者背景の理解不足
病院と在宅側の連携において、情報共有の質は非常に重要です。しかし、現場からは、病院側から提供される「退院時患者情報提供書」に、退院後の課題(身体面、精神面、社会面、環境面)が十分に記載されていないという課題が指摘されています。
また、医療スタッフが患者の背景(介護力、年齢、家族環境)を十分に理解せず、自宅環境が想定されていない福祉用具を指定してしまう、あるいは進行性の疾患の「予後予測」に基づいたケアプラン立案が困難になるなど、生活全体を支える視点が不足していることが、スムーズな在宅療養への移行を妨げています。
第2部:在宅医療の構造的な課題と「24時間対応」の重圧
在宅医療提供者が直面するミクロな課題は、主に「マンパワー不足」と「高負荷な労働環境」に集約されます。
3.1. 深刻な人材不足と高い離職率
医療機関全体の人手不足に加え、訪問看護の現場も人財の確保が困難になっています。2020年の調査では、訪問看護ステーションにおける正規雇用者の離職率は11.5%に達しており、労働力不足が深刻な問題となっています。
この人手不足は、主に以下の要因によって引き起こされています:
- 医療技術の向上による専門性の高い人材への需要増加
- 変則的な勤務形態
- 業務負担の重さ
3.2. 「24時間対応」の重さと低水準な手当
在宅医療の最大の要件の一つが、夜間休日を含む24時間対応体制です。特に在宅医が「一馬力(一人開業)」の場合、夜間休日緊急時対応は救急医療と同様に極めて負担が大きく、そのサポート体制の整備(例:連携、バックアップ病床の確保)が課題となっています。
この24時間対応を支えるための「オンコール待機手当」は、訪問看護ステーションで1日あたり1,000円〜3,000円が相場と、その重責に見合わない低水準で推移しており、労働環境の改善が急務となっています。
第3部:サービス急増の裏側で露呈した「不正」の問題
サービス提供体制の急速な拡大は、残念ながら、質の低下と不正行為の増加という負の側面ももたらしています。
4.1. 行政処分件数の急増
厚生労働省のデータによると、不正請求や基準違反などが発覚したことによる介護事業所(訪問看護を含む)への指定取消・停止などの行政処分件数は、昨年度(2023年度)に139件となり、前年度比で6割増加という急激な増加を見せています。これは、サービス量の増加に伴い、悪質な事業者が参入している実態を示唆しています。
4.2. 不正請求の具体例と構造的な誘因
不正請求の事例としては、居宅介護支援事業所による指定の一部効力停止処分などがあります。これらの不正行為は、主に事業所の収益追求と、行政による指導・監査体制が追いついていない構造的な隙間を突いて行われます。
質の担保がされていない外部委託への依存も問題視されています。在宅医療の現場では、24時間対応のために機能を往診専門クリニックなどに外部委託するケースがありますが、この際、サービスの質の担保がおろそかになる可能性があります。
これらの問題は、単に一部の悪質事業者の問題にとどまらず、地域医療資源の把握と、提供されるサービスの量・質のバランス調整が追いついていないという、構造的な課題の現れであると言えます。
結論:質の高い在宅医療を実現するための道筋
在宅医療の推進は、高齢化する社会において「住み慣れた場所で最期まで暮らしたい」という国民の願いを叶えるための必須の政策です。しかし、その実現のためには、単に「受け皿」を増やすだけでなく、以下の構造改革が不可欠です。
- 病院—在宅間の連携強化と情報連携の標準化: 退院支援を早期に行い、患者の生活全体を考慮した情報(退院後の課題、家族環境、予後予測)を在宅側へスムーズに提供する仕組みを義務化すること。
- 労働環境の抜本的改善: 24時間対応の重責に見合う、診療報酬上の適切な評価と、オンコール手当の大幅な引き上げを通じて、医療・介護スタッフの定着率を向上させること。
- 監視体制の強化と不正への厳正な対処: 増加する不正・基準違反に対し、行政による運営指導の頻度と実効性を高め、悪質な事業者に対しては指定取消などの厳正な対処を徹底すること。
在宅医療が「自宅での療養」という国民の理想を実現し続けるためには、「量」の拡大だけでなく、「質」と「倫理」を担保するための継続的な制度設計と監視が求められています。


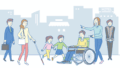
コメント