
導入:マクロとミクロの「ねじれ」— 医療現場が抱える最大のパラドックス
1.1. 日本の医療費が「一般会計の半分」を占める現実
日本の財政構造において、社会保障関係費の占める割合は、少子高齢化の進展に伴い、年々増加し続けています。その規模は国の一般会計を大きく圧迫しており、2022年度の予算においては、社会保障関係費は36.3兆円に上り、これは国(一般会計)の一般歳出の53.8%という過半数を占めるに至っています。この事実は、日本の財政が国民の健康と福祉を維持するためのコストによって、その半分以上が規定されていることを示しています。
さらに、医療、年金、介護を含む社会保障給付費全体は、今後も大幅な増加が見込まれており、2025年度には148.9兆円(対GDP比24.4%)へと急増すると予測されています。特に医療および介護の給付費の伸びが著しく、超高齢社会の進展がマクロ経済に与える圧力は非常に大きいと言えます。
1.2. 現場の悲鳴:国公立病院の深刻な赤字率のデータ提示
マクロな視点で見れば医療費が際限なく増大している一方で、医療提供の現場である個々の医療機関、特に国公立病院の経営状況は極めて危機的であるという、一見すると矛盾した現象が生じています。
厚生労働省が実施した医療経済実態調査(2022年度実績)の結果は、この矛盾を定量的に裏付けています。国公立病院を含む一般病院全体の平均利益率は6.7%の赤字を記録しました。老朽化した設備や施設の更新すらままならないといった報道の背景には、こうした深刻な財政難が存在しています。
対照的に、同じ調査では、一般診療所(クリニックなど)が平均で8.3%の黒字を計上しており、同じ医療提供者間でも経営状況が二極化していることが確認されています。この結果は、医療費増大の「恩恵」が、全ての医療機関に均等に行き渡っているわけではないという、日本の医療制度の構造的な問題を浮き彫りにしています。この矛盾の核となるデータを以下に示します。
マクロとミクロの医療経済パラドックス(概算)
| 指標 | 対象 | 数値(2022年度前後) | 含意 |
| 社会保障関係費の割合 | 国の一般歳出 | マクロでコストは増大 | |
| 一般病院の平均利益率 | 個々の病院(国公立含む) | 6.7%の赤字 | ミクロで経営は悪化 |
| 一般診療所の平均利益率 | 個々のクリニック | 8.3%の黒字 | 医療提供者間で二極化 |
1.3. 本稿の目的:この一見矛盾した現状の背景を構造的に解き明かす
この「マクロの費用増大」と「ミクロの病院赤字」というねじれの根源は、日本の医療制度が持つ独特の構造に存在しています。すなわち、医療サービスが、市場原理ではなく、政府が定める公定価格(診療報酬)によって収益が固定化されている点です。本稿では、増大の要因、赤字のメカニズム、そして公立と個人の決定的な違いをデータに基づき構造的に解説します。
第1部:医療費「増大」の構造的要因(マクロ経済の圧力)
2.1. 超高齢社会の到来:団塊世代の75歳以上層への移行
国民医療費が増加する最大の要因は、日本の人口構造の不可逆的な変化、すなわち超高齢社会の到来です。医療費が高額になる75歳以上人口(後期高齢者)の増加が、医療費全体の伸びを大きく牽引しています。
国民医療費は2022年度に前年度から3.7%増加していますが、この増加傾向は、医療費が特に高額になる高齢者層の割合が増していることに起因します。団塊の世代が次々と75歳以上の後期高齢者医療制度へ移行する「2025年問題」は、単なる人口構成の変化にとどまりません。高齢者が増えるだけでなく、複数の慢性疾患を抱える多疾患併存(マルチモビディティ)の患者が増加することを意味します。結果として、一人当たりの医療費も、医療の複雑性・高度化によって押し上げられ、マクロの医療費増大傾向は今後も継続する構造的な圧力を生み出しています 4。
2.2. 高度化する医療と薬価のインパクト
医療技術の進歩は、国民の健康を向上させる上で不可欠ですが、同時に医療費を増大させる強力な要因です。
近年、特に革新的かつ非常に高額な医薬品が次々と市場に登場しており、現在の薬価制度では、こうした高額薬に対して柔軟に対応できていないという問題が生じています。このため、高額薬価が医療保険財政と国民負担に大きな影響を与えることが懸念されています。
厚生労働省は「国民皆保険の持続性」と「イノベーションの推進」の両立を目指していますが、現実には、高額薬価が財政を圧迫するたびに、診療報酬全体や後発医薬品の価格調整(薬価のマイナス改定)が行われ、財政の均衡を図ろうとする政策的なトレードオフが発生します。これは、革新的な技術導入のコスト増加分が、最終的に医療機関の診療報酬収益の抑制という形で転嫁される圧力となり、病院経営をさらに厳しくする間接的な要因となっています。
2.3. 地域格差と医療資源の偏在
マクロな医療費の増大には、地域間のばらつきも大きく影響しています。国民一人当たりの医療費には依然として大きな地域格差が存在し、最高の高知県と最低の埼玉県では1.44倍もの差があります。
医療費が高い地域は、高齢化率が高い、または地理的にへき地が多く、医療アクセスを維持するために、公立病院が地域医療を担う必要性が高いといった構造的課題を抱えていることが少なくありません。特に公立病院は、採算度外視で地域医療を支える役割(不採算医療、へき地医療)を担うため、高コスト・低効率になりがちな地域の医療提供体制を維持する役割を負っており、これが地域全体の医療費高止まりの一因となりつつ、自らの経営悪化につながりやすい構造を持っています。
第2部:病院「赤字」を生むミクロ経済のメカニズム
マクロの費用が増大しても個々の病院が赤字に陥るのは、収益構造が硬直化している一方で、コスト構造が柔軟に変化しないためです。
3.1. 診療報酬制度の制約:公定価格という名の「天井」
日本の医療機関の収入は、医療行為の対価として厚生労働省が定める診療報酬(公定価格)によって決まります。この公定価格制度は、医療の質を均一化し、政策的な誘導を行うという重要な役割を持っています。
しかし、この制度は病院の収益に対して「天井」を設けることになります。市場原理が働く一般企業と異なり、病院は人件費や物価、高額薬などの原価が上昇しても、自らのサービス価格を設定できません。マクロなコスト増大に対して、診療報酬改定で十分な増額が行われない限り、病院経営はコスト増を吸収できず、収益改善が極めて困難になります。これが「マクロの費用増大にもかかわらず、ミクロの病院が赤字」という矛盾を成立させる最大の構造的要因です。
3.2. 報酬改定の厳しい現実と実質的な収益抑制
診療報酬改定は2年に一度行われますが、その改定率は財政の制約を強く受けています。例えば、2024年度の診療報酬改定では、医療機関の収入に直結する「本体」はわずか+0.88%のプラス改定となる一方、薬価等は-1.0%のマイナス改定となる見込みであり、全体として収益抑制の基調が続いています。
病院経営を圧迫する最大のコストは人件費ですが、少子高齢化に伴うスタッフの平均年齢上昇や人手不足により、必要な人件費は増加しています。人件費や物価の急激な上昇に対して、本体改定率がわずか0.88%程度では、コスト増を吸収することはできません。特に人件費比率が高い公立病院にとっては、この微増では全く追いつかず、赤字が拡大する主要な要因となっています。
3.3. 外部環境による収益圧迫と需要の変化
収益圧迫は制度的な要因だけでなく、外部環境の変化によっても加速しています。
3.3.1. 患者数の減少と需要のシフト
少子高齢化や地方の過疎化に伴い、多くの地域で患者数が減少傾向にあります。患者数が減少すれば、当然ながら診療報酬による収益も減少し、病院の赤字化が進みます。また、新型コロナウイルスの感染拡大期には、多くの人が診療を控えたことも、収益減に拍車をかけました。
さらに、時代の変化に伴い、患者ニーズは入院中心の急性期医療から、介護事業や在宅医療へとシフトしています。これに対応できる病院は患者を集めることができますが、従来の体制を維持している病院は患者を奪われ、収益が悪化する傾向にあります。
3.3.2. 人件費の上昇と負のスパイラル
人手不足が深刻化する中、十分な給与や待遇を用意できない病院では、医療スタッフの離職率が上がり、人手不足がさらに悪化します。人手不足は、医療提供の質の低下とさらなる患者離れを引き起こし、収益悪化と離職の加速という「負のスパイラル」に陥る主要因となっています。
第3部:経営状況の二極化分析:公立病院と個人診療所の決定的な違い
なぜ、医療費が増大する中で、特に公立病院だけが深刻な赤字に陥り、個人診療所は黒字を維持できるのでしょうか。その決定的な違いは、負うべき「政策的使命」と「コスト構造の硬直性」にあります。
4.1. 医療経済実態調査による損益率の比較分析
以下の表は、開設主体別の損益率を示しており、公立病院の経営の脆弱性を明確に示しています(2020年度実績)。
開設主体別 損益率の比較(2020年度実績:単位%)
| 開設主体 | 損益率(補助金なし) | 損益率(補助金込み) | 経営特性 |
| 一般病院全体 | 補助金で辛うじて黒字化 | ||
| 医療法人(病院) | 赤字転落寸前で推移 | ||
| 公立(病院) | △21.4 | △7.3 | 構造的赤字が極めて深刻 |
| 一般診療所(個人) | 高い収益率を維持 (開設者報酬含む) |
この分析結果は、公立病院の赤字が極めて深刻であることを示しています。一般病院全体は、コロナ関連の補助金を投入することで辛うじて0.4%の黒字に転じたものの、公立病院は補助金なしで21.4%もの大幅な赤字を計上し、補助金を含めてもなお7.3%という大幅な赤字から脱却できていません 。このことは、公立病院の赤字が一時的な要因ではなく、その開設主体と運営構造に起因する恒常的な構造的赤字であることを裏付けています。
4.2. 公立病院の構造的赤字の根源
公立病院の赤字は、政策的な使命を果たすための「政策的赤字」の側面と、高コスト体質による「非効率的赤字」の側面が複合している結果です。
4.2.1. 「政策的赤字」の役割:不採算医療・へき地医療の堅持
公立病院は、採算が取れない高度救急、周産期医療、小児科、そしてへき地医療といった、民間では参入が難しい不採算医療を担うことを政策的に義務付けられています。これらの公的サービスは地域住民の生命と安全を守るために不可欠ですが、現行の診療報酬の枠内では十分な対価を得ることができません。
これらの「公的サービス」のコストは、本来、税財源による十分な公的補填で賄われるべきです。しかし、現状ではそのコストが病院の経営上の「赤字」として計上され、公立病院の経営悪化の主要因となっているのです。
4.2.2. 高コスト体質:高い人件費率と医療材料費の傾向
公立病院のコスト構造は、国公立を除く病院と比較して硬直的で高コストになりがちです。
医業収益に対する給与費の比率を見ると、国公立病院は国公立を除く病院よりも顕著に高く(62.4% vs 56.4%)、年々増加傾向にあります。これは、公立病院が高度・救急医療を維持するための常時人員配置が必要なこと、および公共部門特有の給与体系を持つことによるものです。収益の伸びが鈍い中で、この硬直的な高コスト構造は経営を深刻に圧迫します。
また、国公立病院は、高額な医療材料を使用する高度な手術やPCI(経皮的冠動脈インターベンション)などの診療比率が高いと推測されることから、医療材料費の比率も国公立以外の病院より高い傾向にあります。
4.2.3. 非効率性の課題:減価償却費の比率と病床利用率の低下
国公立病院は、大規模な施設や高額機器を保有しているため、医業収益に対する減価償却費の比率も高い傾向にあります(8.1% vs 5.0%)。これは、これらの固定資産の利用率が低いことや、病床利用率の低下を反映していると考えられます。特に公立病院は、へき地など非効率的な経営を強いられる地域を担う側面があるため、高額医療機器の非効率な運用も赤字の要因となりやすいのです。
4.3. 個人診療所の経営戦略と収益構造
一方で、個人診療所が高い黒字率を維持できるのは、経営戦略とコスト構造の柔軟性によります。
個人診療所は、入院を必要としない外来中心の診療に特化し、高コストな救急や高度医療から距離を置くことができます。これにより、大規模な固定資産投資(減価償却費)や、高度医療を支えるための膨大な人件費を低く抑えることが可能です。
また、個人経営は、大規模な公立病院に比べて、患者のニーズの変化(例:在宅医療の需要増加)への対応が迅速であり、経営判断の柔軟性が高いです。診療報酬制度は、低コストで高頻度の外来診療を行う診療所の方が、高コストで複雑な急性期医療を提供する病院よりも、相対的に高い収益率を確保しやすいという構造的な特徴を持っていることも、この二極化を助長しています。
第4部:持続可能な医療提供体制のための改善戦略
マクロの費用増大とミクロの赤字という構造的な矛盾を解決し、国民皆保険の持続可能性を確保するためには、公立病院の役割を再定義し、財源構造を根本的に見直す必要があります。
5.1. 医療機関の機能分化・連携の徹底
全ての病院が全ての医療を担う「フルセット型」体制は非効率であり、経営難の根本原因の一つです。
公立病院は、高度・急性期医療、救急、および不採算医療といった公的機能に特化・集約化し、回復期・慢性期や在宅医療は民間や診療所に任せるという役割分担を徹底すべきです。これにより、公立病院は高額医療機器の利用率向上や経営効率化を図ることができます。
機能分化の推進に際しては、診療報酬制度の制度設計を慎重に行う必要があります。包括払いが過度に急性期医療を抑制し、必要な治療を怠る「粗診・粗療」につながる懸念も指摘されているため、データに基づく丁寧な議論が必要です。
5.2. 公立病院の経営効率化と「政策的赤字」への適切な公的補填
公立病院の赤字解消のためには、効率化努力と公的財源による明確な補填の両方が不可欠です。
5.2.1. 経営形態の見直しとガバナンス強化
硬直化した公務員的な人事制度や給与体系を見直し、地方独立行政法人化など、経営判断の迅速化とコスト削減へのインセンティブが働く経営形態への移行を促進すべきです。柔軟性を確保することで、外部環境に対応できる効率的な運営を目指します。
5.2.2. 「政策的赤字」の財源分離
公立病院が担うべき不採算医療(へき地、高度救急など)のコストを、診療報酬とは別に、税財源からの「公的サービス提供費」として明確に分離し、適切に補填する仕組みを構築すべきです。これにより、病院の赤字が「非効率」によるものなのか、「政策的使命」によるものなのかが明確になり、納税者への説明責任を果たすとともに、病院側も純粋な経営改善目標を立てやすくなります。
5.3. 診療報酬制度の戦略的活用
診療報酬制度を、単なるコスト抑制ではなく、質の向上と効率的な医療を促す仕組みへと進化させる必要があります。具体的には、単なる行為(フィー)に対する支払いから、治療結果(アウトカム)や医療の質を評価する支払いに比重を移すことです。これにより、病院は患者にとって最良の結果を目指すインセンティブが生まれ、医療の質の向上と効率化が両立します。
また、高額医薬品への対応として、費用対効果評価を厳格化し、特定の高額薬剤の使用に対する第三者評価を導入することで、イノベーションと財政持続性の両立を図ることが重要です。
5.4. 医療スタッフの待遇改善と人財確保策
人件費の上昇は経営を圧迫しますが、医療スタッフの離職は医療提供体制の崩壊につながるため、人材確保は最優先課題です。
診療報酬改定において、医療の質を担う専門職の給与・待遇改善に直結する項目を重点的に引き上げる必要があります。公立病院において政策的赤字の補填が実現し、経営が安定化すれば、財源が確保され、医療スタッフへの適切な待遇が提供可能となり、離職を防ぎ、ひいては質の高い医療提供を継続できるという好循環(ポジティブスパイラル)に転換することが可能となります。
結論:日本の医療の未来へ向けて
日本の医療は、高齢化と技術革新によるマクロなコスト増大と、公定価格制度および公立病院の政策的使命によるミクロな収益抑制という、二重の構造的圧力に晒されており、その矛盾が公立病院の深刻な赤字として現れています。
この構造的な矛盾を解消し、持続可能な国民皆保険制度を維持するためには、公立病院の役割を公的機能に特化させ、彼らが担う政策的なコストは税財源で明確に補填する「会計の明確化」と、医療機関全体の機能分化を強力に推進する必要があります。公立病院の赤字問題は、単なる経営問題ではなく、地域社会の医療崩壊を防ぐための国家的な構造改革を必要とする政策課題であると言えます。

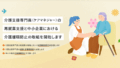

コメント