
令和7年7月28日(月)に、介護労働安定センターから令和6年度「介護労働実態調査」の結果が発表されました。調査結果は、訪問介護業界の現状を読み解く上で非常に重要なデータが満載です。今回は本調査から、特に「訪問介護事業所」に焦点を当ててわかりやすく解説します!
「介護労働実態調査」は、令和6年10月1日~10月31日に実施され、調査対象期日は原則として令和6年10月1日現在のものとなります。調査方法は、自計式郵送方法(一部電子メールによる回収)により、調査対象は全国の介護保険サービスを実施する事業所のうちから18,000事業所を無作為抽出にて選定されました。実効調査数は17,089事業所で、有効回答は9,044件、回収率は52.9%でした。
「介護労働者の就業実態と就業意識調査」は、上記の事業所の介護にかかわる労働者3人を上限に選出し、調査の協力を依頼。 実効調査対象者数は51,267人、有効回答数は21,325件で、回収率は41.6%でした。
訪問介護員の離職率は4年連続で低下! しかし採用活動は依然として厳しい状況
まず注目すべきは、訪問介護員の「離職率」です。
- 訪問介護員の離職率は11.4%で、これは4年連続の低下となります。
- 一方で、「採用率」は14.1%となり、3年ぶりに低下しています。
離職率の低下は良い傾向ですが、採用率の低下幅が離職率の低下幅を上回っているため、介護労働者の「増減率」も低下しています。つまり、辞める人は減ったものの、新たに加わる人も減っており、人手不足の解消にはまだ至っていない状況がうかがえます。
実際に、従業員が「不足している」と回答した事業所の割合は、訪問介護員で83.4%にものぼり、調査対象職種の中で最も深刻な人手不足が浮き彫りになりました。
離職理由のトップは「職場の人間関係」
中途採用で介護業界の仕事に就いた人が、直前の介護関係の仕事を辞めた理由のトップは「職場の人間関係に問題があったため」(24.7%)でした。さらにその具体的な内容を掘り下げると、「上司や先輩からの指導や言動がきつかったり、パワーハラスメントがあった」が最も多く、約半数を占めています。
このことから、職場内のコミュニケーション改善やハラスメント防止策が、離職防止の鍵を握ると言えるでしょう。
訪問介護員の賃金は増加傾向に!
訪問介護員の平均月収(月給)は、前年度と比べて3.2%増加しました。これは、20〜24歳で5.8%増、25〜29歳で5.0%増と、特に若い世代で伸び率が高いのが特徴です。
賃金の向上は、介護職への就職を検討している人にとって大きな魅力となり、採用活動にも良い影響を与えることが期待されます。
サービス提供責任者の役割が離職率低下の鍵に
今回の調査では、「訪問介護・サービス提供責任者」がトピックスとして取り上げられています。
- サービス提供責任者が訪問介護員に対してコミュニケーションや指導を積極的に行うことで、担当している訪問介護員の離職率が低くなる傾向があることが明らかになりました。
- 特に、「仕事上の課題などに関する相談や指導」を実施している場合、離職率が10%未満の割合は63.0%と、実施していない場合(50.5%)と比べて高くなっています。
この結果は、サービス提供責任者が担う訪問介護員へのサポート業務が、現場の安定に直接つながることを示しています。
最後に
令和6年度の介護労働実態調査からは、訪問介護業界が抱える課題と、それに対する希望の光の両方が見えてきました。特に、賃金改善や職場の人間関係改善、そしてサービス提供責任者の適切なサポートが、これからの業界を支える上で重要な要素となりそうです。今後の動向にも注目していきたいですね。
令和7年度介護労働実態調査は、令和7年10月1日を調査基準日として実施を予定しています。私たちも、調査に協力するとともに、その結果に注目してゆきたいと思います。



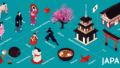
コメント