
介護施設・事業所では、法令や運営基準、加算の算定要件等で、様々なマニュアルや計画書等の作成が義務付けられています。書類仕事ばかりが増えて、現場の負担が増すばかり…、等と文句を言っていても仕方ありません。社会保険料や税金等からなる介護報酬を受け取って事業を営んでいる私たち介護事業所は、書類が法令順守を証明する証となるのです。
でも、とはいっても大変ですよね💦
しかしながら今、そんな状況は変わりつつあると思います。そう、AIの出現と昨今の異様な進化です。
各種マニュアルや計画書等は、どの事業所でも紙ベースで作ってファイリングしているのが普通だと思いますが、作っただけで鍵のかかるキャビネットに入れたまま、ほとんど活用されていない。。。といった事態になっていることが大いに予想されます。それでは意味がありません。
いっそのこと、紙ベースのマニュアルや計画書を全廃してみる、というのはどうでしょうか?
Webアプリ、ホームページといった形で、インターネットから、職員の誰もが、いつでも見ることができる。。。そんなカタチの方がキャビネットに仕舞われている状態よりずっと良いと思いませんか?
今回もGoogleGeminiに生成してもらいました。BCP(業務継続計画)の自然災害編の計画書を作ってもらいました。
以下の資料を参考に、「業務継続計画(BCP)大規模地震編(訪問サービス類型)」をウェブページのスタイルで作ってください。計画書は訪問介護事業所に限定して、自然災害の中でも大規模地震発生時に特化して作ってください。ウェブページはhtmlファイルでお願いします。
・自然災害発生時の業務継続ガイドライン[2.6MB]
・自然災害ひな形(共通)[1.7MB]
・自然災害ひな型(サービス固有)[174KB]
〇〇ケア・サービス
業務継続計画 (BCP) 大規模地震編
〜 大規模地震発生時の業務継続のための行動指針 〜
1. 本BCPの概要 📊
この計画は、訪問介護事業所に特化し、特に大規模地震発生時に、利用者様への介護サービスを継続・早期再開するための羅針盤です。人命の安全確保を最優先に、ヘルパーの皆様が的確に判断し、事業所へ迅速かつ正確に報告するための指針を示します。
皆様自身の安全確保、利用者様の安否確認と緊急対応、そしてスムーズなサービス継続のための連絡・連携に焦点を当てています。
2. 平時からの備えと体制 🎒
有事の際に混乱なく行動できるよう、日頃からの準備と、明確な組織体制の構築が不可欠です。
2.1. 緊急連絡体制の確立と連絡方法 📞
連絡手段の優先順位
- 安否確認システム (例: トヨクモ安否確認サービス) – 🚨 最優先
- 携帯電話(SMS/ショートメッセージ) – 通話困難時有効
- 事業所指定のSNSグループ (例: LINE WORKS, Slack緊急連絡用)
- 携帯電話(音声通話) – 通信集中に注意
- 電子メール – 復旧が比較的早い場合あり
- 災害用伝言ダイヤル (171) – メッセージ共有に活用
- 公衆電話 – 最終手段
- 徒歩での参集 – 事業所指示時のみ、安全に留意
連絡内容のフォーマット(簡潔に)
- ✅ 氏名・所属: 例: 介護員 鈴木
- ✅ 現在の状況: 例: 自宅で被災 / 移動中に被災 / ○○様宅で被災
- ✅ 安否: 例: 無事、負傷なし / 軽傷(右足打撲)/ 中等症以上(骨折疑い、救急要請済)
- ✅ 出勤可否: 例: 出勤可能 / 出勤困難(自宅損壊、交通停止)/ 自宅待機中
- ✅ 利用者様(該当する場合)の安否と状況: 例: ○○様宅、お変わりなし / ○○様転倒、意識あり、軽傷の模様
- ✅ 通信状況: 例: 携帯電話はSMSのみ可 / 公衆電話から連絡
2.2. 情報収集・伝達手段の確保と原則 📢
主な情報収集源
- ✅ テレビ、ラジオ(緊急災害放送)
- ✅ インターネット(気象庁、自治体公式ウェブサイト、信頼できるニュース、SNS公式)
- ✅ 防災行政無線、エリアメール・緊急速報メール、自治体防災アプリ
情報伝達の原則
- ✅ 迅速性: 状況変化を速やかに、判断を支援
- ✅ 正確性: 事実のみ、不確かな情報は伝えない
- ✅ 簡潔性: 要点を絞り、理解しやすく
- ✅ 多角的な手段: 複数の連絡手段を常に意識
- ✅ 個人情報保護: 利用者情報に最大限配慮
2.3. 物資の備蓄 🛒
非常時に業務を継続し、安全を確保するために必要な物資を準備します。
事業所備蓄品リスト (3日分目安)
- ✅ 食料・飲料: 飲料水 (職員1人9L目安)、非常食、簡易調理器具、カセットコンロ
- ✅ 衛生用品: 簡易トイレ、凝固剤、トイレットペーパー、ウェットティッシュ、生理用品
- ✅ 感染対策品: マスク、手指消毒液、防護服、ゴム手袋
- ✅ 救急医療品: 絆創膏、消毒液、包帯、鎮痛剤
- ✅ 情報・照明: 懐中電灯、予備電池、携帯ラジオ、モバイルバッテリー
- ✅ 書類: BCP書面、利用者情報リスト、職員緊急連絡網、ハザードマップ(すべて印刷版)
ヘルパー携行品リスト (常時携帯推奨)
- ✅ 携帯電話、モバイルバッテリー、充電ケーブル
- ✅ 常備薬、持病の薬(予備)
- ✅ 簡易救急セット
- ✅ マスク(予備)、携帯用アルコール手指消毒液
- ✅ ホイッスル、小型懐中電灯
- ✅ 利用者様緊急連絡先カード(最小限情報)
- ✅ 少量のお金(小銭)、身分証明書
- ✅ (可能であれば) 500ml飲料水、簡易栄養補給食
利用者宅で確認すべき備品 (訪問時確認推奨)
- ✅ 飲料水、非常食(最低3日分以上)
- ✅ 簡易トイレ、衛生用品
- ✅ 常備薬、医療器具予備バッテリー、懐中電灯
- ✅ 利用者様の状態に応じた簡易非常用キット
2.4. 職員・利用者情報の把握 📝
- ✅ 職員の役割分担: 緊急時の役割(安否確認、情報収集、利用者支援など)を事前に確認
- ✅ 利用者様の詳細情報: 心身の状態、医療依存度、使用医療機器、内服薬、避難時の介助レベル、災害時の避難場所(指定避難所、親族宅など)を把握
- ✅ 危険区域の把握: 担当エリアのハザードマップ、避難経路、避難場所を事前に確認
2.5. 組織体制と役割分担 👥
指揮命令系統
災害対策本部長: 管理者(〇〇 太郎)
└─ 副本部長: サービス提供責任者(△△ 花子)
└─ 各班リーダー:
├─ 情報収集班リーダー: 職員A
├─ 安否確認班リーダー: 職員B
├─ サービス調整班リーダー: 職員C
└─ 物資調達班リーダー: 職員D
主な役割と担当
- ✅ 管理者(災害対策本部長): BCP統括、対外連携、最終意思決定
- ✅ サービス提供責任者(副本部長): 本部長補佐、BCP実施指揮、職員指示、業務優先順位付け
- ✅ 情報収集班: 災害情報収集、報告集約、情報伝達手段確保
- ✅ 安否確認班: 職員・利用者安否確認、状況把握
- ✅ サービス調整班: サービス提供優先順位再編、人員配置、利用者連絡
- ✅ 物資調達班: 備蓄確認、不足物資の要請・手配
非常時職員参集基準
- ✅ 原則: 自身の安全確保、家族の安全確保が最優先。無理な行動は避ける。
- ✅ 参集判断基準: 自宅・通勤経路の安全確認、交通手段の確保、事業所からの正式要請。
- ✅ 参集連絡: 参集可否と理由を速やかに事業所へ。
- ✅ 徒歩圏内職員の優先: 事業所から徒歩で安全に参集可能な職員は優先的に検討。
3. 大規模地震発生時の対応 🚨
地震発生から復旧までのフェーズに応じた、訪問介護員の対応と報告のフローです。
3.1. 発災直後 (発生から約3時間) ⏱️
- 自身の安全確保:
- ✅ 身の安全を守り、落ち着いて行動。
- ✅ 怪我の有無確認、応急処置。
- 事業所への緊急連絡・報告 (最優先):
- ✅ 自身の安否、現在の状況(場所、自宅/利用者宅状況、移動・出勤可否)を簡潔に。
- ✅ 通信不安定時は、複数手段(SMS, SNS, 171)を試行。
- 利用者安否確認・緊急対応(利用者宅にいる場合):
- ✅ 利用者様の安全確保(家具転倒防止、火の元確認など)。
- ✅ 利用者様の安否(怪我の有無)、部屋の状況(破損、ライフライン停止)把握。
- ✅ 安全な場所へ誘導、避難の必要性を判断し、事業所へ速やかに報告。
- 利用者安否確認・緊急対応(移動中/自宅の場合):
- ✅ 自身の安全確保後、速やかに担当利用者様の安否確認を試行。
- ✅ 安否確認できたら事業所へ報告。
3.2. 応急対応期 (発生から約3時間〜72時間) 🛠️
混乱が収まり、サービス継続に向けた連携を密にする段階です。
- 事業所からの指示確認:
- ✅ 事業所からの指示(優先利用者、サービス変更、移動手段)を待つ、または自ら確認。
- ✅ 不確実な情報に惑わされず、正確な情報に基づいて行動。
- サービス提供の継続判断と優先順位:
- ✅ 事業所と連携し、利用者様の緊急度・重症度に基づき、サービス優先順位を判断。
- ✅ 限られた資源で最低限必要なサービスを継続。
- ✅ 次の訪問先への移動困難時は、状況と理由を具体的に事業所に報告し、指示を仰ぐ。
- 事業所への定期的報告:
- ✅ 自身の状況、利用者様の状況(心身変化、ライフライン、避難状況)、サービス実施状況などを定期的に。
- ✅ 新たな危険箇所や支援ニーズが発生したら速やかに報告。
- 物資の状況報告:
- ✅ 携行品や利用者宅での備蓄品消耗状況を確認、不足時は事業所に報告・相談。
3.3. 復旧期 (発生から約72時間以降) ✅
徐々に通常の生活に戻る段階です。BCPの検証と改善に協力します。
- 通常業務への移行と報告:
- ✅ 事業所指示に基づき、段階的に通常業務へ移行。
- ✅ サービス提供回復状況、利用者様の心身の変化(特に精神的負担)などを引き続き報告。
- BCPの検証・見直しへの協力:
- ✅ 被災経験で感じた課題・改善点(連絡体制、物資、情報共有など)を事業所にフィードバック。
- ✅ ヒヤリハット事例や成功事例も積極的に共有し、組織全体の対応力向上に貢献。
4. 大規模地震発生時の重要連絡・報告事項リスト 📑
訪問介護員が事業所に伝えるべき主な連絡・報告事項を状況別にまとめました。
4.1. ヘルパー自身の状況に関する報告
- ✅ 安否確認: 無事か、負傷の有無、現在地。
- ✅ 出勤可否: 業務継続の可否、出勤困難な理由(自宅被災、交通機関停止、家族状況など)。
- ✅ 移動手段: 利用可能な移動手段と移動経路の安全性。
- ✅ 体力・精神状態: 長時間活動困難な場合や、精神的な負担。
4.2. 利用者様の状況に関する報告(訪問中または訪問予定の場合)
- ✅ 安否確認: 利用者様の安否(無事か、怪我の有無)、意識レベル。
- ✅ 利用者宅の状況:
- 家屋の破損状況(倒壊、ひび割れ、窓ガラス破損など)。
- 室内状況(家具の転倒、落下物、避難経路の確保状況)。
- ライフライン(電気、水道、ガス)の停止状況。
- ✅ 利用者様の心身の状況: 精神的な不安定さ(不安、不眠など)、身体状態の変化、医療機器の動作状況。
- ✅ ご家族の状況: 同居家族の安否、連携状況。
- ✅ 避難の必要性: 利用者様の避難の必要性、介助ニーズ、避難場所の選択肢。
- ✅ 支援ニーズ: 食料、水、衛生用品、医療品などの不足状況。
4.3. サービス提供に関する報告
- ✅ サービス提供の可否: 次の訪問先への移動可否、現在の訪問サービス継続の可否とその理由。
- ✅ 代替サービスの必要性: 自身が提供できない場合の、他のヘルパーによる代替サービスの必要性。
- ✅ 資機材の状況: サービス提供に必要な資機材(マスク、消毒液など)の有無と残量。
- ✅ 実施したケア内容: 緊急時に利用者様に対して行ったケア内容(応急処置、安全確保、声かけなど)。
5. その他重要な留意事項 ✨
- ✅ 無理な行動は避ける: 自身の安全確保が最優先。危険な場所での作業は行わない。
- ✅ 正確な情報伝達: 不確かな情報は流さず、確認が取れた事実のみを伝える。
- ✅ 平常時からの訓練: 日頃からBCPを理解し、事業所と連携して訓練に参加する。
- ✅ プライバシーへの配慮: 利用者様の状況報告時は、個人情報保護に最大限配慮。
- ✅ 連携と協力: 事業所だけでなく、地域の関係機関や住民との連携・協力も意識する。

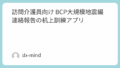

コメント