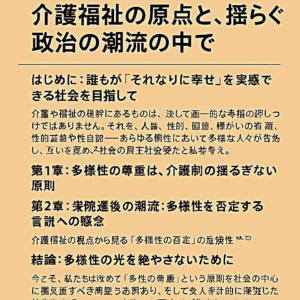
はじめに:誰もが「それなりに幸せ」を実感できる社会を目指して
介護や福祉の根幹にあるものは、決して画一的な幸福の押し付けではありません。それは、一人ひとりがその人らしい生き方を尊重され、それぞれの価値観や願いに沿った「それなりの幸せ」を感じながら生きていける社会を築くことです。年齢、性別、国籍、障がいの有無、性的指向や性自認――あらゆる属性において多様な人々が共生し、互いを認め合い、支え合う社会。これこそが、私たちが目指すべき福祉社会の姿だと私は考えます。
この理念は、決して机上の空論ではありません。むしろ、介護の現場では当たり前のこととして日々実践されている、揺るぎない原則なのです。しかし、昨今の政治的な潮流を見るにつけ、この大切な原則が揺らいでいるのではないかという強い危機感を抱かざるを得ません。
第1章:多様性の尊重は、介護福祉の揺るぎない原則
介護の現場に身を置く私たちは、日々、多様な価値観や背景を持つ方々と接しています。人生の歩み、大切にしてきたもの、そしてこれからどう生きていきたいか。一人として同じ人はいません。だからこそ、私たちは、その人自身の個性や尊厳を尊重し、その人にとって最も望ましい支援のあり方を模索し続けます。
例えば、食事の介助一つをとっても、その人の好みや食習慣、健康状態は千差万別です。画一的なメニューを提供するのではなく、その人の願いを尊重し、可能な範囲で個別的な対応を心がける。排泄の介助においても、プライバシーへの配慮は最も重要です。私たちは、利用者の尊厳を守り、その人らしい生活を支えるために、常に多様な視点を持つことを求められます。
この姿勢は、介護を受ける側だけでなく、介護を提供する私たち自身にも向けられるべきものです。私たち職員一人ひとりの個性や価値観を尊重し、その多様性を組織の強みとして活かしていくこと。それがより良いサービスの提供につながると、私たちは経験上知っています。
多様性の尊重は、単に「認め合う」という受動的な状態に留まりません。それは、それぞれの違いを理解し、尊重し、積極的に社会の中で活かしていくという能動的なプロセスです。異なる視点を持つ人々が共に生きることで、社会全体がより豊かになり、新たな価値が生まれると信じています。
第2章:衆院選後の潮流:多様性を否定する言説への懸念
しかし、先の衆院選後から見られる政治的な動きには、強い懸念を抱かざるを得ません。右派の新興政党が勢力を増し、保守系の党首や政党からは、LGBTQ+に関する法案をはじめ、多様性を担保する政策を否定するような意見が散見されます。
もちろん、現場の運用においては、予期せぬ課題が生じることもあるでしょう。制度設計やその実施には、継続的な見直しと改善が必要です。しかし、だからといって、多様性を尊重するという根本的な立場を揺るがせてはなりません。
多様性を否定する言説は、「みんなと同じであること」を常識として捉え、「異質なもの」を排除しようとする風潮を生み出しかねません。それは、社会の分断を深め、弱者や少数派の人々をさらに周縁化することにつながります。これは、介護や福祉の現場で私たちが大切にしてきた原則とは、全く正反対の方向を向いています。
第3章:介護福祉の視点から見る「多様性の否定」の危険性
もし、政治の場で多様性を否定するような動きが強まれば、それは介護や福祉の現場にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。
- 偏見や差別意識の助長: 社会全体に「違いは良くないものだ」という空気が広がれば、介護を受ける側、提供する側双方に偏見や差別意識が生まれる可能性があります。それは、信頼関係を築く上で最も大切な「人間性への尊敬」を蝕むものです。
- 制度からの排除: 多様性を考慮しない法律や制度設計は、介護を必要とする人々の一部を、サービスや支援の対象から排除してしまう可能性があります。例えば、戸籍上の性別と異なる性自認を持つ人々が、適切なサービスを受けられないといった問題が起こり得ます。
- 個々のニーズへの対応の困難化: 画一的なサービス提供が常識となれば、利用者の個別的なニーズに合わせた柔軟な対応が難しくなります。それは、介護の質そのものを低下させ、利用者の尊厳を傷つけることにもなりかねません。
私たち介護・福祉の専門職は、こうした事態を深く憂慮しています。なぜなら、それは私たちが長年かけて築き上げてきた、「誰もが自分らしく生きられる社会」を目指すという理念を根底から覆すものだからです。
結論:多様性の光を絶やさないために
今こそ、私たちは改めて「多様性の尊重」という原則を社会の中心に据え直す必要があります。それは、単なるスローガンではなく、具体的な政策として、そして社会的な意識として、社会全体に浸透させていかなければなりません。
教育の現場では、多様な価値観や生き方を学ぶ機会をさらに充実させる必要があります。メディアは、偏見を助長するような報道を避け、多様な人々の声に耳を傾けるべきです。そして政治の場では、一部の意見に偏ることなく、すべての人々の権利と尊厳を守るための議論と政策実現が求められます。
私たち介護・福祉の専門職は、日々の実践を通して、多様な人々が共に生きる社会の可能性を現実のものに変えていく使命を担っています。利用者の笑顔と、その人らしい人生を支えることこそが、私たちの存在証明です。
今回の衆院選の結果は、私たちに改めて社会のあり方を問いかける機会を与えてくれました。多様性を尊重し、誰もが「それなりに幸せ」を感じられる社会を築くという、介護福祉の原点を決して忘れることなく、私たちはこれからも声を上げ続け、実践し続けていきたいと思います。多様性の光を社会の隅々まで届けられるように、ともに歩んでいきましょう。

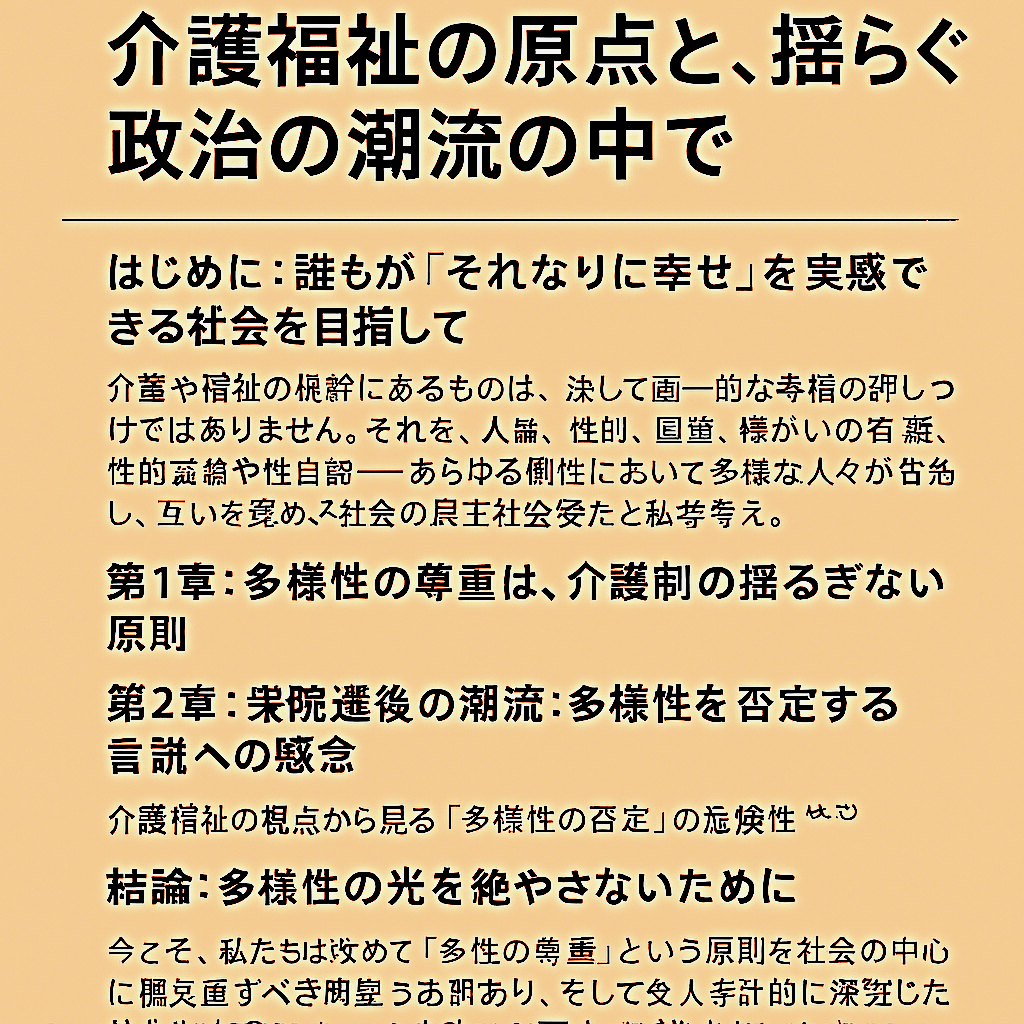

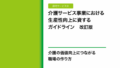
コメント