
訪問介護の現場では以前、日々のサービス提供記録は紙に書くことが多く、複写式の記録用紙の一枚を利用者宅に残し、押印された記録用紙を事業所に保管するパターンが多かったです。記録用紙は月末にヘルパーが事務所に持ってきて、サービス提供責任者が記録の確認をするため、月初は前月の実績確認と請求事務で大忙しでした。
ところで、訪問介護においては、スマホでサービス提供記録を入力したり、勉強会や会議もスマホでおこなうことが多くなりましたが、登録ヘルパーという雇用形態がある訪問介護事業所においてはスマホは会社支給のものではなく、個人のスマホを仕事で使うことになります。
ITパスポートの資格取得の勉強をする中で学んだことですが、これは『BYOD(Bring Your Own Device)』というれっきとした名前の付いたものであることを知りました。その際の注意やセキュリティ対策など、法人として整備しなければならない事項があることを学ぶことができました。
最近では紙の記録用紙から、スマホでサービス提供記録を入力・送信する方式が広まってきました。各種加算を取る上でも、介護ソフトの導入やスマホでサービス提供の際の指示を伝達したり、サービス提供記録の入力をしたりすることが多くなりました。
実はコロナ禍が、介護業界のデジタル化を強烈に推し進めてきた現状があります。もちろん、他の業種、業界でも同じかと思います。
新しい仕組みを導入することは一部の人からは反発を受けることも多いのですが、対面での活動が制限されていたコロナ禍だからこそ、「コロナだから仕方ない」で、デジタル化を後押しするきっかけとなりました。
コロナ禍はある意味、時代の変化を加速させました。厚生労働省からの伝達や各種会議のオンライン化、Zoom研修など、介護業界においても、コロナ禍前とコロナ禍以降では、ビジネス環境が激変しました。今や、オンラインツールは、訪問介護においても、高齢のヘルパーさんにとっても当たり前の時代となりました。
介護の法定研修では、事故再発防止や個人情報保護の取り組みなどが義務化されています。デジタル化が進展している現在では、かなりのアップデートが必要になります。今の時代、介護業界においても、最低でも各法人に一人以上、できれば各事業所に一人以上の『ITパスポート(情報処理技術者)』の国家資格を有するスタッフが必要なのではないかと感じています。また、そのような時代のアップデートに付いていける社長、経営者、管理者、施設長、所長などの配置は必須だと思うのです。
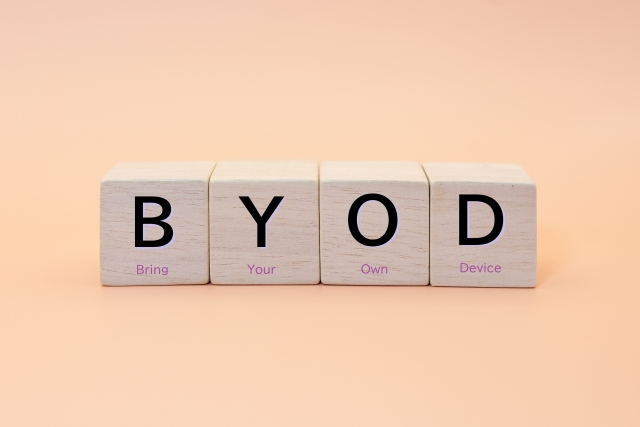


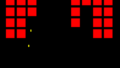
コメント