
介護事業所では運営基準で、介護事故の再発防止策の策定と運用、事故やヒヤリハット事案の記録が義務付けられています。訪問介護では、事故再発防止委員会の開催が年1回以上の開催や研修が必要です。
皆さん介護事業所で働いている人の多くは「ヒヤリハット報告書」なるものをを書いたことがあると思います。そういう私も何度も書きました。
サービス提供責任者である私は、都道府県に報告・提出する「事故報告書」も書いたことがあります。都道府県の担当者からのヒヤリングや関係機関への報告など、事故発生から数週間は眠れないほどのストレスを感じたこともありました💦
一般的に「ヒヤリハット」は、事故に至らない事案を指しています。
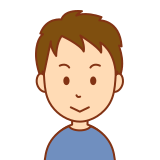
介護事業所の「介護事故」と「ヒヤリハット」の違いって、何なんですか?
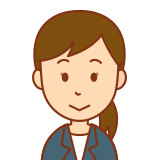
「介護事故」と「ヒヤリハット」は、介護現場でよく使われる用語ですが、意味が少し異なりますよ
介護事故は、介護サービスの提供中に発生する事故を指します。具体的には、利用者が怪我をしたり、健康状態が悪化したりするような事態を意味します。例えば、利用者が転倒して怪我をしたり、誤って薬を飲んでしまったりする場合が該当します
一方、ヒヤリハットは、事故に至らないものの、潜在的な危険がある事案を指します これは、事故が起きる前段階の状況を指し、例えば、利用者が転んでしまう可能性がある状況や、薬の誤投薬の可能性がある状況などが該当します
要するに、介護事故は既に発生した事故を指し、ヒヤリハットは事故が発生する前の潜在的な危険を指します。どちらも重要な対応が求められますが、ヒヤリハットは早期に対策を講じることで事故を未然に防ぐことができますよ
何か他に知りたいことがあれば、教えてくださいね
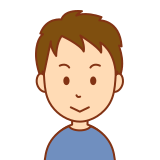
ありがとうございます 事故とヒヤリハットの違いがよくわかりました
もちろん、運営基準の主旨は介護事故を防ぐことにあります。現場の課題を洗い出して、再発を防止することが目的です。
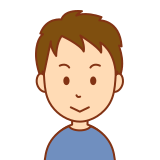
それって、よく言われている「PDCA」サイクルで実施するっていうことですか?
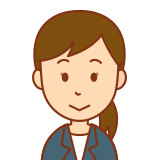
はい、そうですよ PDCAサイクルは、あらゆる場面で活用できる考え方なんです
PDCAサイクルは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善)の4つのステップからなる継続的な改善プロセスです 次のような流れで進行しますよ
Plan(計画):目標を設定し、達成するための計画を立てます
Do(実行):計画を実行します
Check(評価):実行した結果を評価し、問題点や改善点を洗い出します
Act(改善):評価の結果を基に、計画を改善し、次のサイクルに反映します
PDCAサイクルは、業務の効率化や品質向上を目指すためのツールとして広く利用されているんです
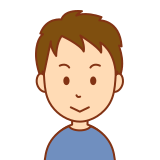
ありがとうございます よくわかりました 介護事故の再発防止とヒヤリハット報告に当てはめて考えると、次のようになるんでしょうか?
Plan(計画):『事故・ヒヤリハット再発防止』の基本方針をつくって、その基本方針に基づいて具体的な対策を計画する
Do(実行):その基本方針と事業所が取り組もうとしている具体的な対策をヘルパーさんに周知して、私たちサービス提供責任者は具体的な対策を実行する
Check(評価):常に状況を確認して、ヒヤリハット事案が発生したらヘルパーさんと一緒になぜ起こってしまったのか、どうしたら起きないですんだかを話し合って報告書を書いてもらう
Act(改善):サービス提供責任者同士が集まって年1~2回以上、委員会を開いて、個々のヒヤリハット事例を検証、再発しないような新しい方針や対策を話し合う
Plan(計画):個々のサービス提供責任者が経験した知恵を出し合って共有して、新しい基本方針や具体的な対策をつくったり見直したりする
Do(実行):新しい基本方針や見直した具体的な対策をヘルパーさんに周知して、私たちサービス提供責任者は具体的な対策を実行する
以下続く。。。
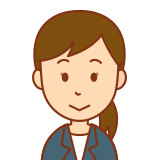
ベリーグッドです!
PDCAサイクルに加えて「SECI(セキ)モデル」という考え方もあるんですよ
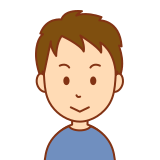
セキモデル?、何ですか、それって??
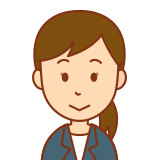
SECIモデルは、知識創造のプロセスを表すフレームワークで、共同化(Socialization)、表出化(Externalization)、連結化(Combination)、内面化(Internalization)の4つのプロセスから構成されます。これらのプロセスは以下のように進行します。
共同化(Socialization):暗黙知を他者と共有するプロセス。例えば、ベテラン社員が新入社員に対して直接体験を通じて知識を伝える場面。
表出化(Externalization):暗黙知を形式知に変換するプロセス。知識を文書化したり、図解化したりすることで他者と共有。
連結化(Combination):異なる形式知を組み合わせて新たな知識を創造するプロセス。複数の資料やデータを統合して新しい理解を得る場面。
内面化(Internalization):形式知を個々人が体験を通じて暗黙知として体得するプロセス。新しい知識や技術を実践し、自己のスキルにする場面。
ようするに、個々の事例、個々のヘルパーさんやサービス提供責任者が経験したことや学んだこと(暗黙知)を全員で共有して、事業所全体のスキルアップ(形式知)にしてゆき、それをまた個々のヘルパーさんやサービス提供責任者が実践してゆく(暗黙知のアップグレード)という考え方と方法なんですね
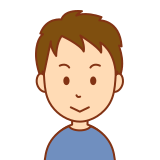
おーっ、そうゆうことか!
すばらしい。。。
PDCAサイクルも、SECIモデルも素晴らしい見かたですね!
この二つのとらえ方を合わせると、もっと良い方法になる気がします
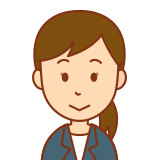
するどい! そうなんですよ
PDCAサイクルとSECIモデルを統合することで、知識創造と業務改善の両方を効果的に推進できるんです
Plan(計画):SECIモデルの表出化と連結化プロセスを活用し、新たな知識やアイデアを計画に反映。例えば、過去の成功事例やデータを基に計画を立案。
Do(実行):計画を実行する際にSECIモデルの共同化プロセスを活用し、チーム内での知識共有と協力を促進。
Check(評価):実行結果を評価する際に、SECIモデルの内面化プロセスを通じて得られたフィードバックや改善点を反映。
Act(改善):評価結果を基に、次の計画を立てる際にはSECIモデルの表出化と連結化プロセスを再度活用し、新たな知識やアイデアを取り入れる。
このように、PDCAサイクルとSECIモデルを統合することで、継続的な改善と知識創造を両立させて、事業所全体の効率と革新性を向上させることが期待できますよ
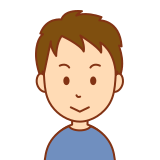
ありがとうございます!
運営基準でやらなきゅいけないと、義務的、形式的にやってしまっていたような気がしますが、ちゃんとやると事故も防げてヒヤリハット事案も改善して、事業所にとってもヘルパーさんにとっても、私たちサービス提供責任者にとっても、WinWinになりますね 今回はありがとうございました とっても参考になりました 勉強になりました 仕事のやりがいが高まった気がします!
ヒヤリハットは事故に至らない事案を指していますが、もしかしたらヒヤリハットの中に、介護事故にお相当するレベルのものも含まれているかもしれません。事業所においておこなう「事故(ヒヤリハット)再発防止委員会」を義務的、形式的に実施するのではなく、本当に介護サービスの質を高めるために活用してゆく必要があります。これにより、利用者にとっても働く人にとっても、質と環境の向上につながってゆくのだと思います。



コメント